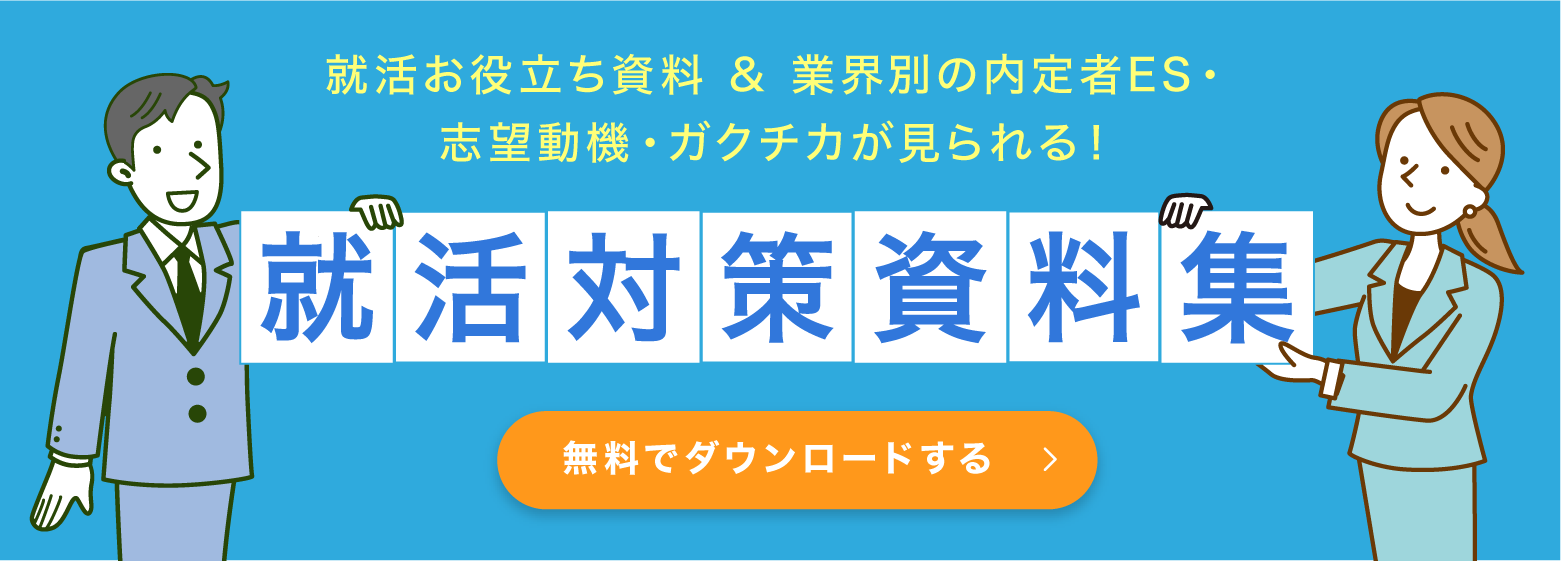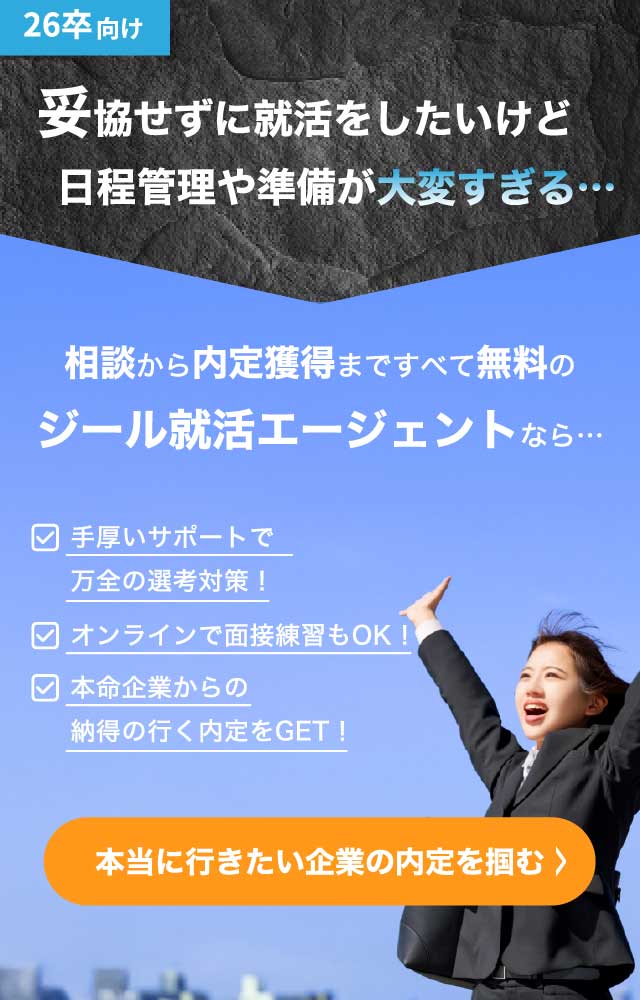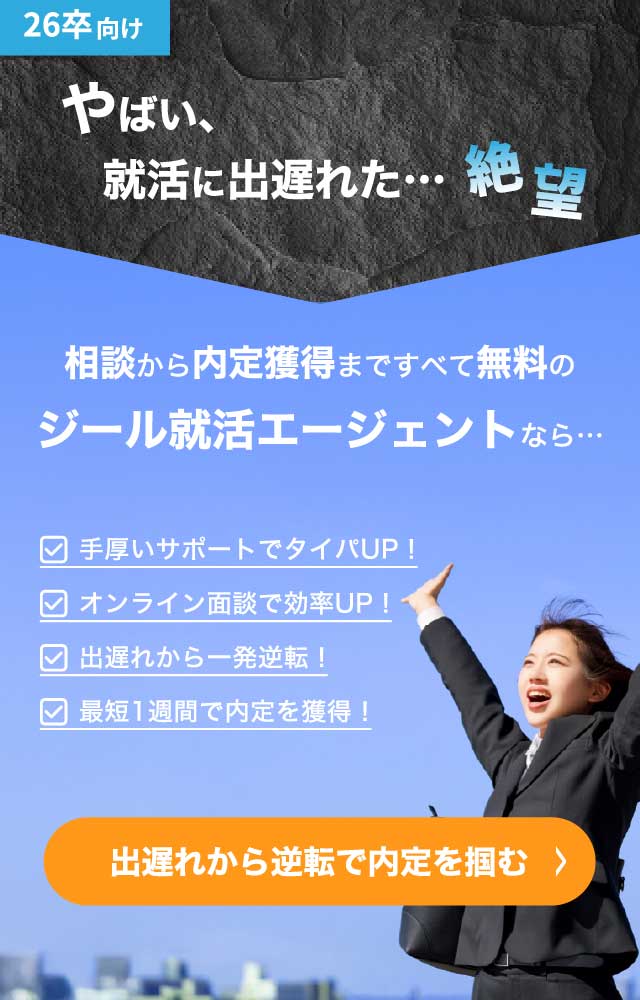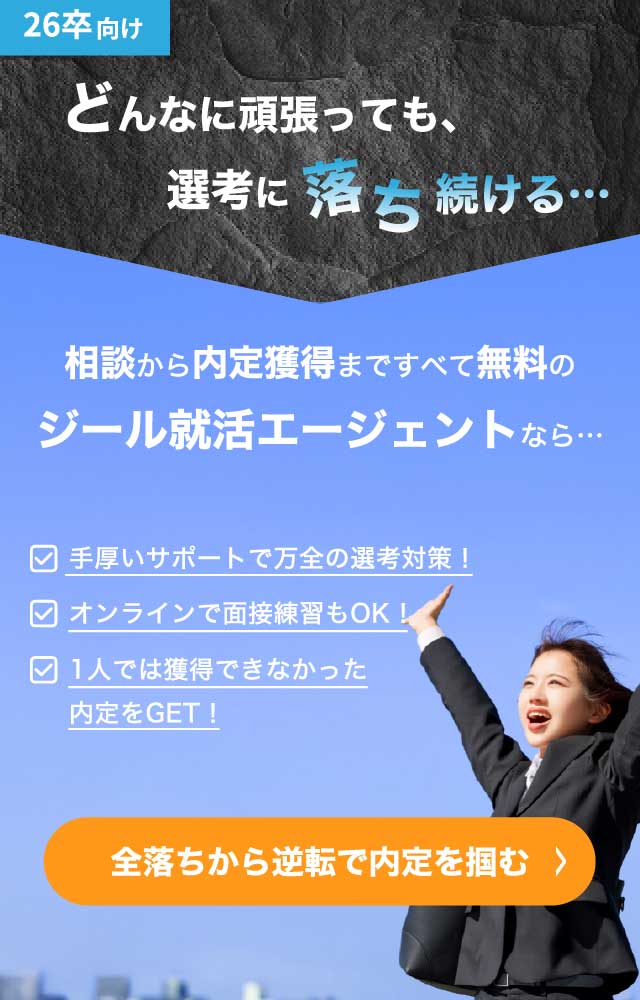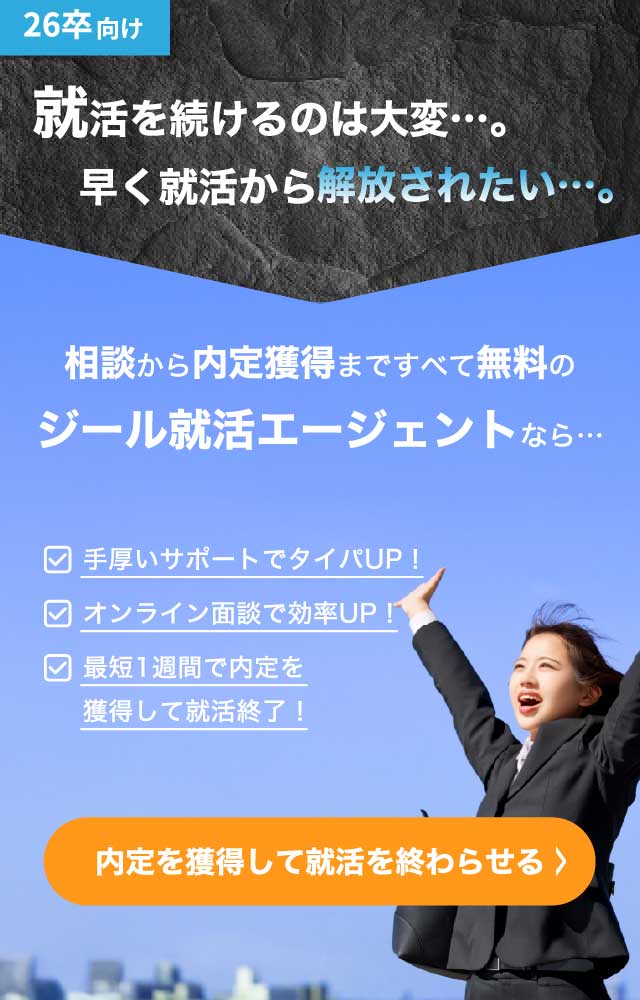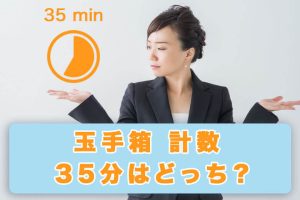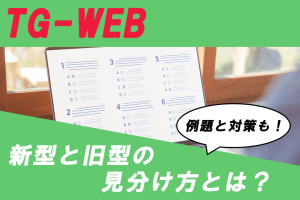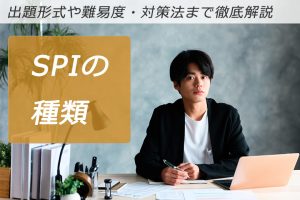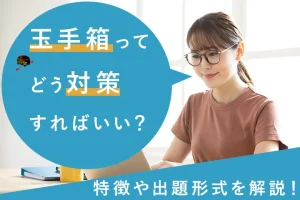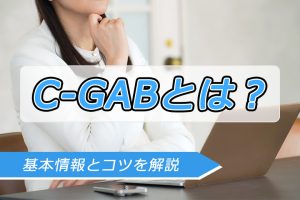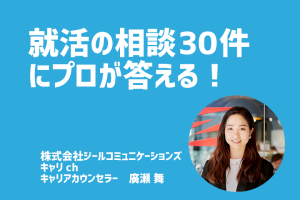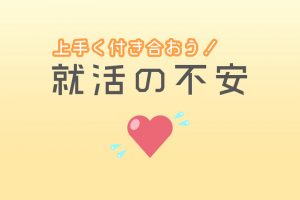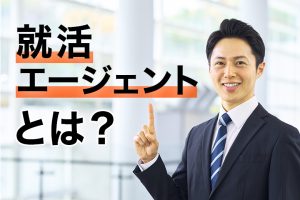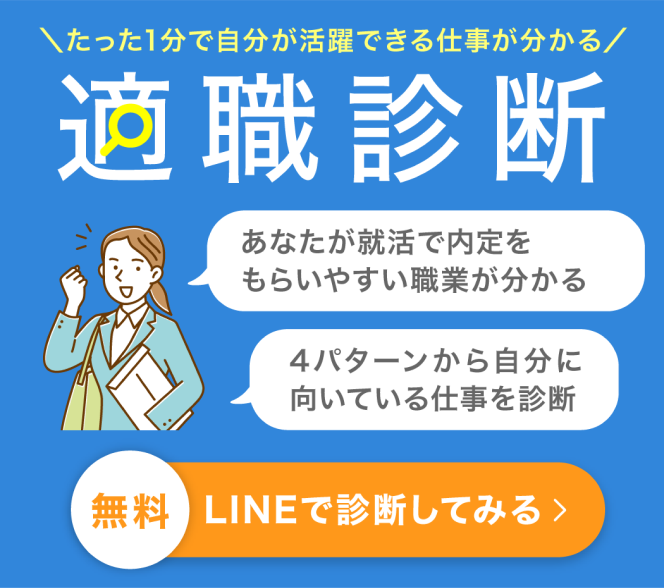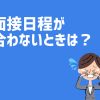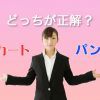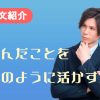SPI対策が間に合わない!適性検査でボロボロにならない方法
2025年8月12日
この記事でわかること
SPI対策が間に合わないと、就活で不利になる
SPI対策が間に合わない場合も、毎日コツコツ勉強しよう
SPI対策が間に合わないと思ったときは、時間の使い方が重要
本当に間に合わないなら、SPI対策が不要な求人を探す手もある
「就活始めたてで何をすれば良いか分からない」という人がまず使うべきツール
- 【これだけで完璧】自己分析ワークシート
✅就活の軸や譲れない条件が明確になる - 【就活で失敗しないため】就活まるわかりガイド
✅内定者の就活スケジュールなどが分かる - 【就活必需品のリストが見れる】就活グッズ&持ち物リスト
✅スーツやバッグの選び方のポイントも解説
- 【これだけで完璧】自己分析ワークシート
「就活で失敗したくない」なら、就活のエキスパートに相談するのがおすすめ
- ジール就活サポート
✅数多くの内定獲得を実現してきた就活のエキスパートが自己分析までサポート
- ジール就活サポート
「就活やることが多くてしんどい...」という人が持っておくべきツール
- 【企業選びに役立つ】業界研究ガイド
✅主要業界8選を網羅 - 【まずは適職を探そう!】職種マップ
✅職種40種類を分野別に解説
- 【企業選びに役立つ】業界研究ガイド
\サービス利用登録者数16万人以上!/

SPI対策が間に合わないそうですね?
 キャリアアドバイザー 廣瀬
キャリアアドバイザー 廣瀬
 就活生 Aさん
就活生 Aさん
そうなんです。やらなきゃとは思ってたんですが、気づいたらこんな時期になっちゃって焦ってます。もし対策が間に合わなくてSPIがボロボロだったら、もう内定は無理なんでしょうか?
そこまで悲観しなくても大丈夫。時間があんまり取れない中でもできる対策はありますし、どうしても対策が間に合わないならSPIを回避するという手もあります。
 キャリアアドバイザー 廣瀬
キャリアアドバイザー 廣瀬
 就活生 Aさん
就活生 Aさん
ホントですか!?詳しく教えてください!そんなウルトラCがあるなら知りたいです!
では今回は、SPI対策に必要な時間や今からでもSPI試験に間に合う対策のコツについて解説しますね。本当に間に合わない場合の内定獲得法も紹介するので、安心してください。
 キャリアアドバイザー 廣瀬
キャリアアドバイザー 廣瀬
目次
就活って最初に何をしたら良いの?
「いざ就活初めてみると何をどの順番ですれば良いか分からない...」という方は、「自己分析ワークシート」でまずは自己分析してみてください。
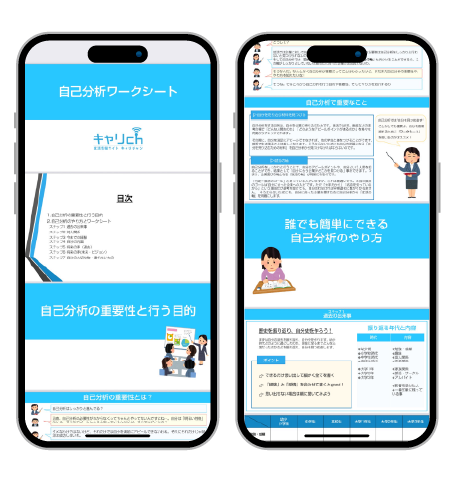
自己分析ワークシートは、たった1日で自己分析が完結し、自分に向いている仕事や業界がわかり、受けるべき企業が明確になります。
「就活迷子になって就活失敗したくない...」という人の強い味方なのでぜひ自己分析ワークシートを使って納得の内定をもらってくださいね!
\ たった1分で自己分析が完結する! /
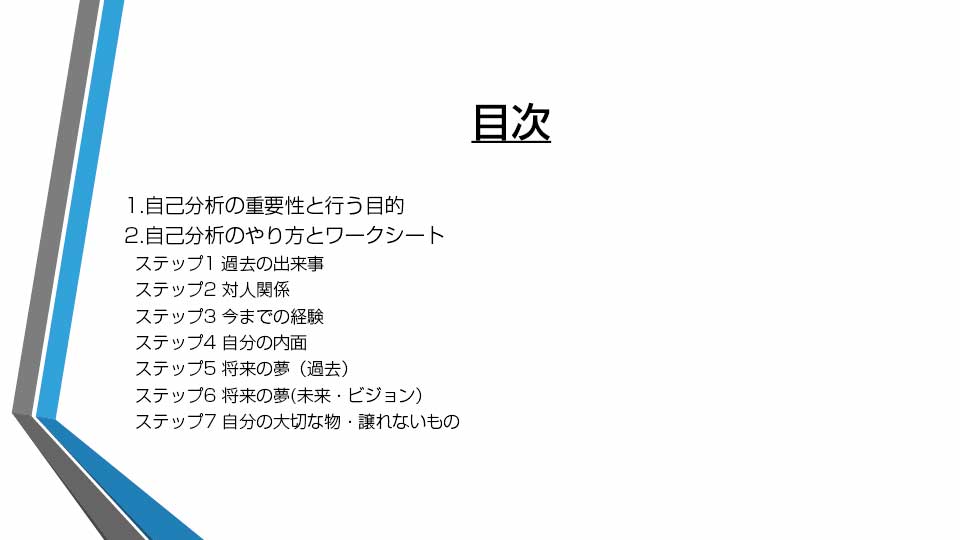
間に合わないからといってSPI対策をしないと就活に不利

もしも「もう間に合わない」と諦めてしまってSPIの勉強をしない場合、残念ながら内定獲得において固い確率で不利になるでしょう。その理由は、以下の4つです。
そのため、たとえ間に合わないと感じても、諦めずに少しずつでも勉強を進めることをオススメします。
それぞれの理由について以下で詳しく説明するので、SPI対策を諦めかけている人はぜひ参考にしてください。
採用選考にSPIを実施する企業が多いから
SPIの勉強をしないと内定獲得において不利になる理由の1つは、新卒の採用選考にSPIを取り入れている企業が非常に多いためです。
新卒の採用選考において企業は、以下のような目的をもって適性検査を実施します。
- 一定以上の基礎学力を持っているか確認するため
- 多すぎる候補者を足切りするため
- 自社への適性を客観的に診断するため
- 面接時の参考にするため
- 面接ではわからない部分を知るため
- 適性のある配属先を見極めるため
そして、現在の新卒採用において、最も普及している適性検査がSPIです。そのため、もしも「対策が間に合わない」という理由でSPIの勉強を諦めてしまったら、選考にSPI試験を取り入れている多くの企業で落ちる可能性が高くなります。
もちろん、採用選考でSPIを実施しない企業もないわけではありません。しかし、SPIを実施する企業に比べて企業数が少ないため、それでなくても時間がないという中で、自力でそれを探すのは現実的ではないでしょう。
応募先の選択肢が限られますし、そこから自分の適性や希望に合う企業を探そうと思ったら、なおのこと企業探しが大変になってしまいます。
ただし、SPIは単に学力を測るだけの試験ではありません。SPIのための勉強が間に合わないなら、性格検査でライバルと差をつける手もあります。実は、多くの企業が学力と同じくらい「性格検査」の結果を重視しているからです。
無料の就活支援サービス「スピード内定サポート」では、経験豊富な就活エージェントがあなたの性格を分析し、性格検査の結果で「高評価」を期待できる企業をピンポイントに紹介。学力テスト対策とは別の角度から、内定獲得を強力にバックアップします。
まずはどんな企業と相性が良いか、相談してみませんか?ESの添削や面接へのアドバイスも受けられるので、時間のかかる学力テスト対策よりも確実かつ効率的に内定率を高められますよ。
出題パターンが独特だから
SPI対策が間に合わないと落ちる人が多い理由は、出題パターンに慣れていないと解けない問題が多いからです。SPI試験で出題される問題の多くは、中学生・高校生レベルの問題なのですが、いくら学力が高くても慣れていないとミスが起こりやすい形式で作られています。
そのため、対策本や問題集を活用して出題パターンや傾向を掴んだり、苦手分野を何度も復習して慣れていくことが必要なのです。
また、企業が合格ラインとする正答率に満たない人は、簡単に足切りされます。合格ラインはSPI受験者の平均よりも高く、目指したい企業の合格ラインを目標に勉強しないとほとんどの人が落とされてしまうのです。
このように、「出題パターンへの慣れ」と「企業が合格ラインとする正答率に近づけること」を目標に対策を打つべきですが、なぜこれをクリアしないと落ちる確率が上がるのか、詳細な理由を説明します。
なお、SPIで落ちる人の特徴は過去のコラムでも紹介しているので、こちらも参考にしてください。
関連コラム
SPIを適当に埋めると落ちる!合格する3つの対策や問題を紹介
出題数に対して試験時間が短いから
対策が間に合わないからと言って勉強を諦めてしまうと選考に受からない理由には、出題数に対して試験時間が短いことも挙げられます。
先ほど説明したように、SPI試験で出題される問題は、基本的に中学生・高校生レベルの問題です。しかし、過去にやってきたテストのようにはいきません。出題数が多いにもかかわらず試験時間が短いため、単純に知識を持っているだけでは時間内に回答を終えることすらできないのです。
下記は、テストセンターで出題される分野の科目と時間配分の目安です。
| 分野 | 出題される分野 | 制限時間 |
|---|---|---|
| 言語 |
|
言語・非言語合わせて35分 |
| 非言語 |
|
|
| 英語能力 |
|
20分 |
これだけ多くの出題内容に対して短い試験時間であることを加味すると、1つの設問に対して即座に解答できる力を身につける必要があります。頭で覚える対策と同時に、体で慣れる対策も必要なため、日々コツコツ練習をしていく必要があるのです。
採用選考におけるSPIの合格ラインが高いから
勉強をしないと受からない理由には、採用選考におけるSPIの合格ラインが高いことも大きいです。
採用選考のSPIでは、中小企業なら正答率70%以上、大企業なら正答率80%以上、とくに人気の高い大手有名企業なら正答率90%以上が合格ラインだといわれています。
大手企業狙いの就活生は非常に多く、ただでさえ狭き門です。さらに大手企業は能力の高い人を採用したいため、まずSPIの結果で判断してふるいにかけるのでしょう。
なお、SPIの平均正答率は50%〜60%の間と言われています。中小企業でも70%以上の正答率が必要である点を考えると、勉強量が不足して平均程度しか正答できない場合、ほとんどの企業のSPI試験に落ちてしまうことになるわけです。早めの段階で対策を打っておく必要があります。
特に大手に入りたい人は、模試などを繰り返して自分の平均正答率を徐々に上げていき、合格ラインまで目指していく必要があります。
「自己分析ワークシート」ならたった1分で自己分析が完結する
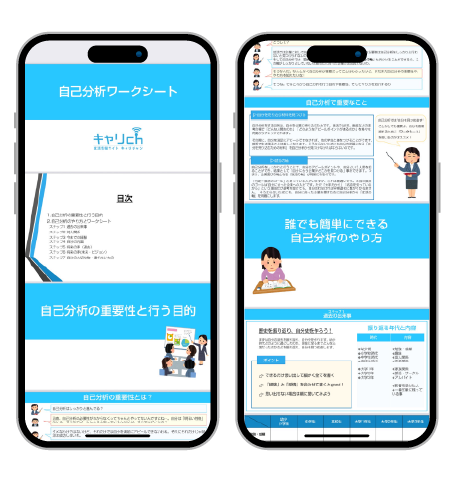
ワーク形式で就活の軸や譲れない価値観、向いている仕事まで分かる
就活のエキスパートが監修しているので自己分析で失敗しなくなる
人事に高評価な長所と短所も見つかるので内定がもらいやすくなる
\たった1分で自己分析が完結する!/
▶︎ 自己分析ワークシートをもらう本当に間に合わない?SPI対策に必要な時間とスケジュール

「SPI対策が間に合わない」と焦っている就活生はまず、本当に間に合わないのか検証してみましょう。
確かに、SPI対策を始める理想的な時期は、卒業前年度(大学3年生)の12月と言われています。しかし、その時期に始めないと本当に間に合わないのでしょうか。
次の章で説明しますが、SPI対策を全くしないというのは就活の上でリスクが高いです。そのため、チャレンジする前から「もう間に合わない」と諦めてしまう前に、以下の3点を確認することをオススメします。
まずは、就活の全体の流れをふまえつつ、SPI対策に必要な勉強量に関して説明します。本当に間に合わないのか判断する上での参考にしてください。
SPI対策に費やすべき時間
SPI対策の勉強時間は、最低でも30時間(理想は60時間)はとっておくことをオススメします。
なぜこれだけ多くの時間を費やす必要があるのかというと、SPIで対策を打つべき分野・科目の種類が多いことと、複雑な形式の試験問題に慣れるための練習をする必要があるからです。
SPIの試験では性格検査以外に言語分野・非言語分野の能力検査がありますが、企業によってはそれに加えて、英語能力検査や構造的把握力検査の受験も求められます。各分野の問題の形式は、学生が今まで受けてきたテストの形式と違うため、時間をかけて慣れる必要があるのです。
採用情報解禁時期に慌てて勉強を始める人もいますが、対策の進め方としては1ヶ月〜2ヶ月くらいかけて、1日1時間程度のSPI対策をルーティーンにして積み重ねていくのが理想です。勉強時間が30時間だと仮定すると、1ヶ月かけて毎日1時間勉強を繰り返した場合と一度に30時間勉強した場合とでは、圧倒的に前者の方が覚えられるからです。
人間が短時間で覚えられる量は少ないので、余裕を持って毎日コツコツ勉強することが大切です。1日数分でも勉強時間を設けて、徐々に進めることをオススメします。
なお、「30時間」という数字を見て、目の前が真っ暗になってしまった人もいますよね。「ESや面接対策で手一杯なのに、ここからSPIの勉強時間を捻出するのは不可能に近い」と感じているかもしれません。
そんな就活生には、無料の就活支援サービス「スピード内定サポート」の利用がオススメです。企業探しや業界・企業研究、ES・面接対策など、その他の対策にかかる手間と時間を就活のプロに任せることで、SPI対策に集中できます。
プロに頼める部分は頼んで、あなたの貴重な時間は1問でも多く問題を解くために使った方が内定率を高めるはずです。非効率な就活から解放されて、あなたにしかできない「SPI対策の時間」を確保しませんか?
就活におけるSPIのスケジュール
「SPI対策が間に合わない」と焦っている人が次に確認すべきは、就活におけるSPIのスケジュールです。いつまでに対策を仕上げる必要があるのかわからないと、間に合うのか間に合わないのか判断できません。
政府呼びかけによる就活ルールに沿って採用選考を行う場合、SPI試験は以下の通り大学4年の6月以降に実施される運びとなります。
- 3年生6月…インターン、自己分析、業界分析を開始
- 3年生3月…企業のエントリー受付開始
- 4年生5月…ESを終える
- 4年生6月〜9月…SPI試験、面接
- 4年生10月…内定式
ただし、年々就活が早期化しているため、SPI試験と面接を6月以前に実施する企業も多数あります。そのため、1ヶ月以上(30時間以上)の勉強時間が必要であることを加味すると、5月ギリギリにSPI対策を終わらせるのでは間に合わない可能性が高いです。
また、近年の傾向ではESの提出と合わせてSPI試験の実施を求める企業も増えており、早ければ3月のエントリー受付と同時にSPI試験を受ける可能性があります。
それに加えて、早期選考を受ける場合はこの限りではありません。その場合は早期選考のスケジュールにおいてESを提出するタイミングか、1回目の面接が行われる前後のタイミングでSPIを受けることになるでしょう。
逆に言うと、就活ルールより遅い時期に採用選考を受ける場合も、その選考におけるES提出時期か1回目の面接の前後にSPIを受けることになります。そのため、SPIを受ける時期も遅くなり、必ずしも対策が間に合わないとは限らないことを覚えておきましょう。
SPI対策で一夜漬けはOK?
SPI対策において、一夜漬けで勉強する方法はオススメできません。なぜなら、一夜漬けで臨むとケアレスミスが増えるからです。
SPIは出題数が多いにもかかわらず、試験時間がかなりタイトです。素早く理解する読解力が必要なため、睡眠不足で頭が冴えていない状態で臨むと本来のパワーを発揮できずに、ミスを連発してしまう可能性が高まります。
また、人間が短時間で覚えられる量には限界があります。一夜漬けで詰め込みすぎると、せっかく勉強した内容も蓄積されず、勉強していない人と同じ知識量になってしまいます。毎日1時間でも勉強したり模試を行ったりすることで慣れていくものなので、同じ時間と量だとしても毎日繰り返して進める方がオススメです。
SPI対策における理想の勉強スケジュールとしては、まずは毎日1時間対策本で少しずつ進めていき、SPI試験が近くなったら苦手分野を中心に対策をしていくやり方です。SPI試験前日に勉強する分野は苦手分野だけにするなどして、効率よく知識を入れていきましょう。
SPI対策が間に合わないときに意識すべきコツ
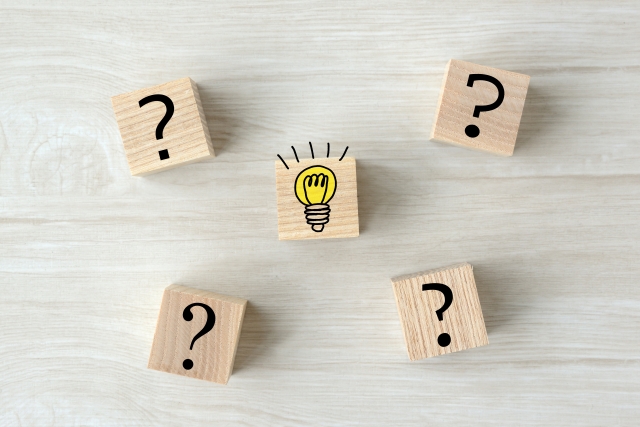
周りよりも少し遅くSPI対策を始める人は、いかに効率的に知識を取り入れるかが重要です。以下のような方法で、効率よく進めていくことをオススメします。
SPI対策が間に合わないという事実は変えられませんが、遅れを取り戻すことはいくらでもできます。短期間で効率よく勉強を進めるための近道を4つ紹介するので、これから勉強を進めていく上での参考にしてください。
【1】時間の使い方に気を付ける
SPI対策は非常に多くの知識を取り入れなければならないと同時に、制限時間に左右されずにサクサク解答できるように問題への慣れが必要です。そのためには、毎日対策本や問題集をコツコツと進めていけるように時間の使い方に配慮しましょう。
理想の勉強時間は30〜60時間なので、1日1時間〜2時間の勉強を1〜2ヶ月かけてこなしていくことをオススメします。
しかし、たいていの大学生は、アルバイトやサークルでも忙しく毎日を過ごしています。毎日ルーティーンで同じ時間を作ることが難しい人も多いでしょう。それでもしっかり時間を作るためには、「スキマ時間」を見つけて有効活用するとよいです。
例えば、電車で通学している人なら「〇〇駅〜〇〇駅まではSPI対策本の時間」など、1日のうち手があく時間を見つけてSPI対策の時間と決めます。スキマ時間はほんの数分だったとしても、毎日複数のスキマ時間を合わせれば、1日1時間の時間を作ることはさほど難しくないはずです。
【オススメのスキマ時間の有効活用例】
- 朝の通学時、電車に乗る15分間は問題集の解説を読む
- バイト先に着いたらバックヤードで5分間だけ頻出問題を見る
- 帰宅後、入浴中に10分間対策本を読む
- お風呂から上がったら30分間練習問題を解く
- …これだけで1時間になります。
【2】実戦に近い形式に慣れる
対策本を読み込む時間より、問題集や模試などなるべく実践に近い形式で勉強する時間を多くとる方が効率的です。人間は頭で覚えるよりも、体で慣れる方が身につきます。
対策本を読んで考えすぎるより、とにかくたくさんの問題を解いてミスを繰り返す方が短期間で多くの学びを得られます。早い段階で「なぜミスしたのか」という根本的な要因を解明することができますし、苦手分野に対しての課題解決が早くなるのです。
また、毎日のスキマ時間を使って進めるなら、問題集を活用しましょう。分野ごとの練習問題を空いた時間に埋めていくようにするとストレスなく進められます。例えば、「この10分間のスキマ時間は、言語分野の長文読解の問題を5問解く」など目標を設定して進めるのがオススメです。
SPIは限られた時間で多くの問題を解答しなければなりません。「この時間に対して何問解く」というように、小さくても目標設定をして進めていくと徐々に慣れていきます。
そして、40分以上時間が取れそうな時は定期的に模試をやってみることをオススメします。毎日コツコツ練習してきたことが実際の試験ではどのくらいサクサク進められているかの確認ができることと同時に、実際の試験と同じ制限時間で行ってみることで体が慣れていきます。
なお、SPIの問題集はキャリチャンでも提供しているので、ダウンロードして活用してください。
【就活対策資料】
SPI解説付き問題集
【3】分野別に優先順位をつける
SPI対策が間に合わない時期の勉強は、分野ごとに優先順位をつけて進めていくと効率的です。一度に全ての分野を網羅するように勉強すると、頭が混乱して入るべき知識が抜けていく可能性もあります。
よって、まずは言語と非言語で分野別に進めていき、そこから苦手分野を探っていく方法で進めることをオススメします。
SPIは苦手分野を潰していくことと、頻出問題に慣れることが正答率アップの鍵です。そのため、苦手分野から解決していき、あとは頻出問題に対する解答をいかに速く正確にできるかを目指して段階的に練習すると効率的に対策を進められます。
苦手分野を避けたくなる人が多いですが、「苦手分野=もっとのびしろがある分野」であるととらえて欲しいです。ここがクリアできれば正答率が大きく変わることになるので、難しくても頑張って勉強してください。
また、毎回出てくる頻出問題は頭に入れておきたいので、対策本を活用しましょう。対策本には頻出問題が載っています。得意不得意にかかわらず覚えておきたいところです。
なお、苦手分野を後回しにするように、自分と相性の悪い企業に時間を割いてしまうのは非常にもったいないことです。勉強の優先順位づけと同時に、「企業選び」の優先順位も見直しませんか?
無料の就活支援サービス「スピード内定サポート」では、あなたの性格特性にマッチする企業をプロが代わりに探し出します。あなたがSPIの頻出問題対策に集中している間に、「性格検査で有利になる企業」をリストアップしてくれる便利なサービスです。
就活全体を賢く、効率的に進めることで、少しでもSPI対策避ける時間を確保しましょう。
【4】苦手分野は解説まで読む
先ほど説明した通り、苦手分野の克服こそが正答率アップの鍵になります。苦手分野の勉強には時間をかけて欲しいです。
問題集を用いる時、得意分野はスピード重視で時間配分に慣れることにフォーカスしてサクサクと解答してOKですが、苦手分野は解説までじっくり読むことが大事です。解説を読み込んでいくと、「なぜ間違えたのか」の根本が理解できるので、他の同様の問題が出題されたときにもその考え方を応用して解答できます。
このように「なぜその答えになるのか」を突き詰めて考えられるようになれれば、いつの間にか苦手分野が得意分野になりますよ。
また、何度も間違えてしまう問題には、対策本や問題集に付箋やマーカーでチェックしておくことをオススメします。ミスした問題に対する解説はスキマ時間を利用して読む癖をつけましょう。
まだ間に合う分野別のSPI対策<言語>
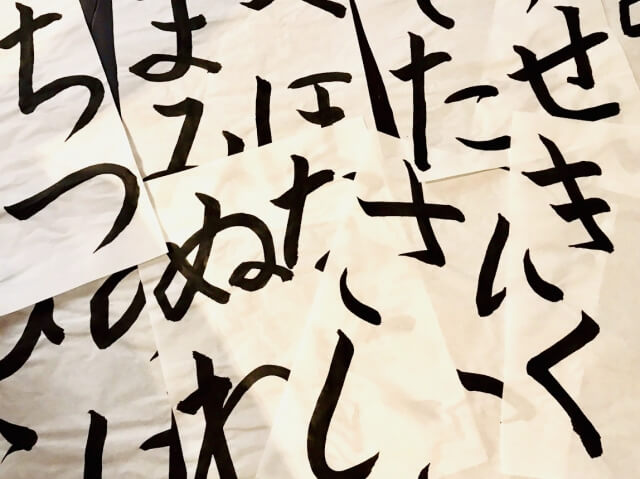
言語の試験では、主に下記の分野が出題されます。その中でも優先して勉強しておきたい分野が「二語の関係」「語句の意味」「長文読解」の3つです。
- 二語の関係
- 語句の意味
- 語句の用法
- 文の並び替え
- 空欄補充
- 長文読解
- 同義語・反義語
- …その他
「二語の関係」「語句の意味」「長文読解」の3つは、設問の意図を理解するまでに時間がかかるため、SPIの言語問題の中でもっとも難しいと言われています。つまり、この3つを制することが早い段階で正答率アップに近づけられる鍵だといえるでしょう。
そのため、ここではSPI対策が間に合わない就活生のために、「二語の関係」「語句の意味」「長文読解」の3分野に絞って対策法を紹介します。ぜひ試してみてください。
二語の関係
「二語の関係」は、与えられた二つの語句に関してそれぞれがどういった関係になるのかを答える設問です。
- 【例題】
- 次に示された二つの語句の関係を考えて、同じ関係のものを選びなさい。
- 「車:運転」
- ア iPhone:スマホ
- イ テレビ:視聴
- ウ 日食:月食
- (A)アだけ
- (B)イだけ
- (C)ウだけ
- (D)アとイ
- (E)アとウ
- (F)イとウ
上記の例文の答えは「(B)イだけ」です。これを解説すると、「車:運転」という語句は目的語と動詞の関係にあたるので、「車を運転する」と文章にできます。
これと同様の関係にある語句を選択肢から選ぶとすると「イ テレビ:視聴」が該当することが分かりますね。(テレビを視聴するという文にできる)
SPIの場合、このような二語の関係性がどこに分類されるかを問われる問題の種類は、下記8つが頻出とされています。
- 含む
- 対立
- 役目
- 原材料
- 同じ意味
- 仲間
- 一組
- 目的語と動詞
これらはSPIの頻出問題なので、提示された2つの単語がどの関係性に分類されるのかを瞬時に読み解けるように力をつける必要があります。
そのためのコツは、まずは上記8つの分類を丸暗記し、そのあと頻出する語句をマスターすることです。これをまず覚えたら、二語を文章に置き換えて考え、問題を解いてみましょう。例えば「たんぽぽ:花」だとしたら、「たんぽぽは花の一部である」と文章にすることで「含む」の分類に該当することが分かります。
こうして段階的に慣れていくことで、徐々に解答スピードが増していくので、毎日のスキマ時間のトレーニングに取り入れることをオススメします。
語句の意味
「語句の意味」は、与えられた問題文に対して意味が合致する語句を選ぶ設問です。
- 【例題】
- 次の文の言葉と合致した意味の語句を一つ選びなさい。
- 「見せかけだけの勢い」
- (A)威厳
- (B)趨勢
- (C)虚勢
- (D)威風
- (E)威圧
上記の例文の回答は「(C)虚勢」となります。(虚勢とは、見せかけだけの勢いのこと)
見てわかるように、同じような漢字を使った熟語がたくさん出てくるので、ケアレスミスが起こりやすい問題です。
さらに、日常生活では馴染みのない熟語も入ってくるので、語彙力を増やすことが最初の対策と言えます。とはいっても、語彙力を急に増やすことはできないので、短期間で対策をするためにはSPI対策本を利用しましょう。
特に言語分野の頻出問題が多い対策本であれば、出題パターンがつかめてきますし、自然と語句の知識をつけられます。また、余裕があれば新聞などの活字に触れる機会を作っておくと良いでしょう。
長文読解
「長文読解」は、文字通り長文で記載された文章の内容に対して、設問に答えていく問題です。1,000文字以上の長文を読んで内容を理解した上で解答しないといけないので、時間切れになることがリスクとして挙げられます。
時間切れで後の設問が解答できなくなるともったいないので、これを防ぐためにはいかに効率的に内容を把握できるかがポイントです。そのためのコツとして、以下の2つが挙げられます。
- 最後の段落を先に読む
- 次に設問を読む
日本語の文章は基本的に起承転結の形式で書かれているため、最後の段落さえ読めば、題材となっている長文が何について書かれている文章でその結論が何なのか一瞬でわかります。全文を読むことなく、全体像を把握できるわけです。
全体像を把握したら、次に設問を読むことをオススメします。なぜなら設問を読むことで、何に気をつけて本文を読めばよいのか把握できるからです。
結論がわかっており、問われることもわかっていれば、それ以外の部分を読み飛ばしても問題ありません。あとは速読の要領でポイントをかいつまみながらサクサク読み進め、設問にかかわる部分が出てきたらその場で回答も同時に進められます。
この2点の対策だけで、長文読解の問題が制限時間に間に合わない事態を飛躍的に減らせるでしょう。
まだ間に合う分野別のSPI対策<非言語>
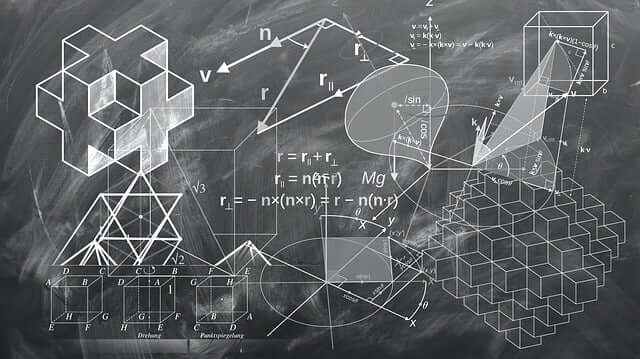
非言語の試験では下記の問題が出題されますが、中でももっとも難しいと言われている分野が「推論」と「図表の読み取り」の2つです。
- 推論
- 図表の読み取り
- 集合
- 順列・組合せ
- 確率
- 割合と比
- 料金割引
- 損益算
- 仕事算
- 代金精算
- 速度算
この2つは設問に対して考える時間が多く、ケアレスミスも起こりやすい分野です。ですから今回はSPI対策が間に合わない就活生のために、「推論」「図表の読み取り」にフォーカスした対策方法を紹介します。
推論
「推論」は、与えられた情報から正しい事柄を読み取る問題です。
【例題】
モール、スーパー、薬局、雑貨屋に、A、B、C、Dの4人が2店ずつ買い物に行った。E〜Hが次のように語ったとき、正しいものは次のうちどれか。ただし、A、B、C、Dの4人が、3人以上同じ店に揃うことはない。
- E:「私は薬局でAとDに会った」
- F:「私とCとBが雑貨屋にに行った」
- G:「私はAとCにスーパーで会った」
- H:「私はBとDにモールで会った」
(回答群)
- ア:Aはモールに行った
- イ:Dは雑貨屋にに行った
- ウ:Aはスーパーに行かなかった
- エ:Bは薬局に行かなった
この解答は「エ」になります。
例題を見て感じるように、推論は他の問題よりも時間をかけて考えないと解答を導き出せません。そのため、推論以外の設問に回答する時間を短くして、推論に時間をかけられるように配分しましょう。文章を読み込まないとミスしやすいので、内容をかいつまんで速読するのではなく、しっかり読むことが重要です。
また、選択肢の文章表現はばらついていることが多く、慣れていないと理解するのに時間がかかります。その際は、表現の仕方を自分で直して統一させるとわかりやすいです。
問われている内容を紙に書き出してみる方法もオススメです。紙に書くことで視覚的に理解できるので、設問との関連性が見えて解答が早くなります。図にできそうなら図にしてみたり、わかりにくい文章は重要な語句をかいつまんで情報を整理したりするとよいでしょう。
対策本や問題集で練習をする際は、必ず解説まで読むことをオススメします。推論で問われている内容や設問の仕方が幅広いので、問題のパターンがつかみにくいです。しかし解説を読めば、同様の問題に対しても耐性ができてきてパターンをつかむことができます。
この後紹介するオススメ対策本も参考に、推論の対策に適した対策本で練習をしましょう。
図表の読み取り
「図表の読み取り」は、提示されたデータ(図表)から問われる設問に答える問題です。
【例題】
A社では宅配便の大きさによって配送料が異なります。大きさと配送料は下記の表です。
| 大きさ | 10cm未満 | 10-30cm未満 | 30-100cm未満 | 100cm以上 |
| 配送料 | 300 | 500 | 600 | 800 |
大きさが50cmの荷物と1m20cmの荷物を二つ送るとした場合、料金はいくらになるか。
- (A)1400円
- (B)1700円
- (C)880円
- (D)1200円
この例題の答えは「(A)1400円」となります。単純に表の通り「600+800」の答えです。
通常は設問から読んで表→選択肢の順番に読むことが多いと思いますが、これを時間を短く効率よく回答するには設問から読むことがコツです。
図表はこれ以外にももっと複雑で読みにくいものも多く、読み込んでしまうと時間がとられてしまいます。時間を短縮できるよう、言語の長文読解でも出てきた「設問から読む」ことをクセづけして練習しましょう。
SPI対策が間に合わない人向け|オススメの対策本
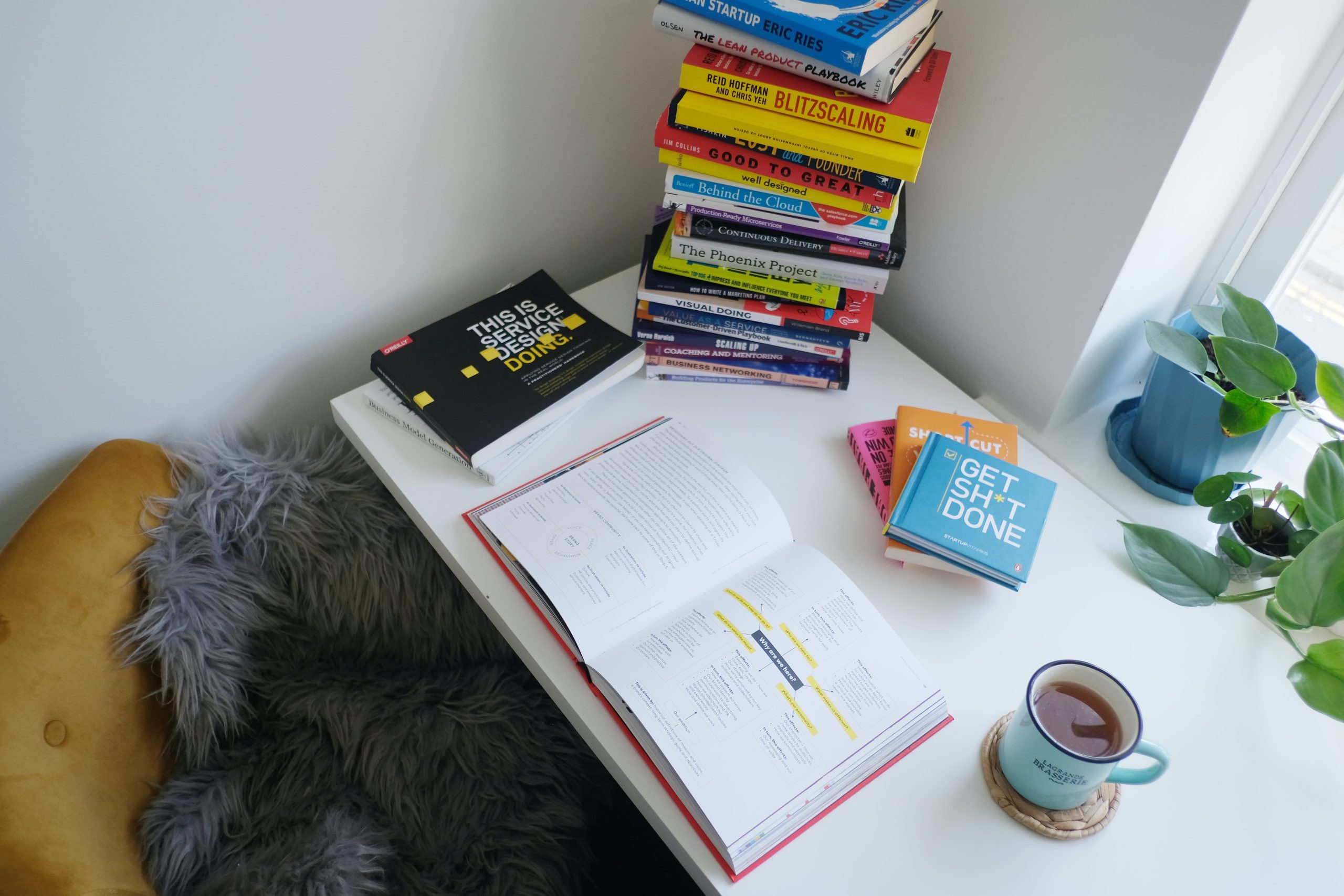
周りの就活生よりも時間がなく「SPIまで間に合わない!」と感じている学生は、短期間で上手に知識を詰め込めるような対策本を選ぶことが大事です。といっても、書店や通販サイトには色々な種類の対策本がありすぎて迷うと思うと思うので、以下の2つを紹介します。
対策本選びの参考にしてください。
SPI対策本の選び方
SPI対策における対策本の選び方としては、「種類」「発行年」「問題数」の3つをチェックすることがオススメです。
まずは「種類」についてですが、SPIには高卒向けなど様々な種類が存在します。大学生の皆さんが受けるSPIは「SPI-U」という種類なので間違えないようにしましょう。加えて、受験方法(テストセンター、Webなど)に応じて対策本が違うので、受けるテストの形式も確認する必要があります。
また、発行年も要チェックすべき部分です。書店には最新の発行年の書籍を中心に置いていますが、ネット通販だと2〜3年前の対策本を間違って買ってしまうこともあります。最新版の方が今の傾向に似ているので、必ず発行年を確認した上で購入してください。
そして、短期間でSPI対策をしなければならない人は「問題数」も確認しましょう。短期間でのSPI対策は、苦手分野を反復して練習しながら慣れることを意識していただきたいので、例題が多ければ多いほどオススメです。
書店で購入する際は、ぜひ問題数と苦手分野がどれだけ豊富に記載されているかも確認してください。
SPI対策本のオススメ5選
ここでは、毎年評価が高く通販サイトでも口コミが高い対策本を紹介します。いずれも短期間でSPI対策をする人にオススメな本なので、「対策が間に合わない!」と焦っている就活生はぜひ参考にしてみてください。
■ SPI対策が間に合わない人向けの対策本【1】|情報が網羅されたタイプ
- 最新! SPI3完全版
- 著者:柳本 新二
- 出版:高橋書店
テストセンターとWebテスティングに対応した対策本です。情報が網羅されているので1冊持っておくとスキマ時間の勉強に使いやすくて便利です。
■ SPI対策が間に合わない人向けの対策本【2】|短期間集中型タイプ
- 7日でできる! SPI必勝トレーニング
- 著者:就職対策研究会
- 出版:高橋書店
こちらは短期間で詰め込めるような問題集で、まさに今焦りを感じている人にオススメです。
■ SPI対策が間に合わない人向けの対策本【3】|圧倒的問題数のタイプ
- 史上最強SPI&テストセンター超実践問題集
- 著者:オフィス海
- 出版:ナツメ社
こちらは問題数がとにかく多く、数がこなせます。苦手分野はとにかく反復して練習した方が良いのでオススメです。
■ SPI対策が間に合わない人向けの対策本【4】|解説がわかりやすいタイプ
- 本気で内定! SPI&テストセンター1200題
- 著者:ノマド・ワークス
- 出版:新星出版社
こちらも問題数が多い問題集です。解説の文章がわかりやすいのもポイント。
■ SPI対策が間に合わない人向けの対策本【5】|問題の再現度が高いタイプ
- SPI3&テストセンター出るとこだけ!完全対策
- 著者:就活ネットワーク
- 出版:実務教育出版
テストセンターに特化した対策本。テストセンター独自の問題を再現しているので、模試感覚で勉強できます。
SPI対策が本当に間に合わない場合の内定獲得法

SPI対策がどうしても間に合わない人や、対策を頑張っても「もうお手上げです…」という人が内定をもらえないかというと、そうではありません。SPI対策なしでも、内定を獲得する方法はあります。
ここではその方法を、以下の2点から解説しましょう。
その流れと方法を次から説明します。
SPI対策が不要な企業にエントリー
SPI対策がどうしても間に合わない人や、対策を頑張っても「もうお手上げです…」という場合には、SPI対策なしで受けられる企業にエントリーするという選択肢もあります。
本来SPI試験は大手や人気企業を狙う学生だけでなく、中小企業やベンチャー企業からの内定をもらいたい学生にとっても欠かせない試験です。まさに就活の第一関門とも言えるので、就活生は必ず対策することをオススメします。
しかし、どうしても対策が間に合わない場合は、SPI対策なしに内定を獲得できるようなルートを持っておくと良いでしょう。
SPI対策なしに内定を獲得できるとは、たとえば以下のような企業です。
- 採用選考の際にSPI試験を実施しない企業
- 学力検査の成績で足切りを行わない企業
ほとんどの企業はSPIを実施していることは前提ですが、実はSPIなしで選考をする企業も少数ながらないわけではありません。
また、SPIそのものは実施するものの、学力検査の成績で足切りを行わない企業もあります。そうした企業は性格検査のためにSPIを取り入れているだけなので、学力検査のための試験勉強は不要です。
ただし、前述のように「SPIを実施しない」「学力検査の成績で足切りを行わない」といった条件を絞り、就活生が自力で企業探しを行うことはあまり現実的ではないでしょう。そうした企業の見つけ方は次項で説明するので、そちらを参考にしてください。
SPIを実施しない企業に出会うには
新卒の採用選考で「SPIを実施しない」「学力検査の成績で足切りを行わない」といった企業を探すには、下記3つのパターンがあります。
- 就活エージェントからSPI対策なしで内定可能な企業を紹介してもらう
- キャリアセンターの職員に探してもらう
- インターン経由で面接を受ける(インターン経験者のみ)
上記の中でも、SPI対策が不要な企業に最も効率よく出会うためには、就活エージェントから紹介をしてもらうことがオススメです。就活エージェントは契約企業の選考傾向について詳しく把握していますし、例年SPIで悩む就活生をサポートしているので、そうした条件指定の企業探しの体制ができています。
ただし、「SPIを実施しない」企業だけに絞った就活をするのはもったいないです。「学力は自信ないけど、人柄には自信がある」そんなあなたの強みを活かせる企業は、あなたが思うよりずっと多く存在します。
数ある就活エージェントの中でも、ジール就活の無料支援サービス「スピード内定サポート」なら、「SPIなし」の求人はもちろん、「SPIは実施するけれど、性格検査の結果を重視してくれる企業」の紹介も得意です。
選択肢を狭め過ぎず、多様な選択肢の中から納得のいく内定を目指しませんか?SPIが不安なあなたのための特別な選考ルートも用意しているので、ぜひ相談してみてください。
SPI対策が間に合わない場合も内定を諦める必要はない
SPIは非常に多くの企業で採用選考に取り入れられているため、間に合わないと思っても諦めずに可能な限りの対策を行うことをオススメします。なぜなら、全く対策をしないと就活においてかなり不利になるからです。
短時間でも効果が上がる方法はあるので、少しずつでも対策しましょう。
それでも、どうしても対策の時間が取れない、効果が上がらないといった場合は、SPIを避けて就活する方法もあります。その場合は自力での企業探しが難しいので、就活エージェントなどに求人を紹介してもらうとよいでしょう。
いずれにしても、SPI対策が間に合わないからといって、就活そのものを諦める必要はありません。自分の状況に合ったやり方で、内定獲得を目指してください。
「スピード内定サポート」に参加しよう!
SPI対策が間に合うかどうかに関するQ&A
SPIの勉強をしないとどうなる?
SPIの勉強をしないと、高確率で落とされます。SPIで合格ラインとされるのは、中小企業なら正答率70%以上・大企業なら正答率80%以上です。平均正答率が50〜60%なので、勉強をすることがいかに重要かが分かります。
SPIの勉強には何か月必要?
理想の勉強時間は30~60時間ですが、毎日コツコツ続けることで覚えていくものなので、1〜2ヶ月くらいかけて勉強することをオススメします。
SPI対策はいつまでに仕上げるべき?
SPI試験が始まる1ヶ月前くらいが理想です。なお、SPI試験の開始時期は6月からが基本ルールですが、近年では早まっている傾向にあるので、3月ごろには仕上げておくと安心でしょう。
この記事の監修者

廣瀬 舞
株式会社ジールコミュニケーションズ
HR事業部マネージャー
大学卒業後、教育機関を経て入社。7年間、キャリアカウンセラーとして新卒・中途・既卒求職者の就職を支援し、これまでに4000名以上の求職者を担当し内定まで導いている。女性ならではの親切丁寧な対応が定評を呼んでおり信頼度が厚い。
就活支援の得意分野は「面接対策」。特に現代ならではの動画面接、オンライン面接の対策実績は1000社以上、2000名以上を支援してきた実績がある。
また、これらの知見を活かして学校におけるキャリアガイダンス セミナー内容の監修、講師を務めるなど、幅広くキャリア育成に尽力している