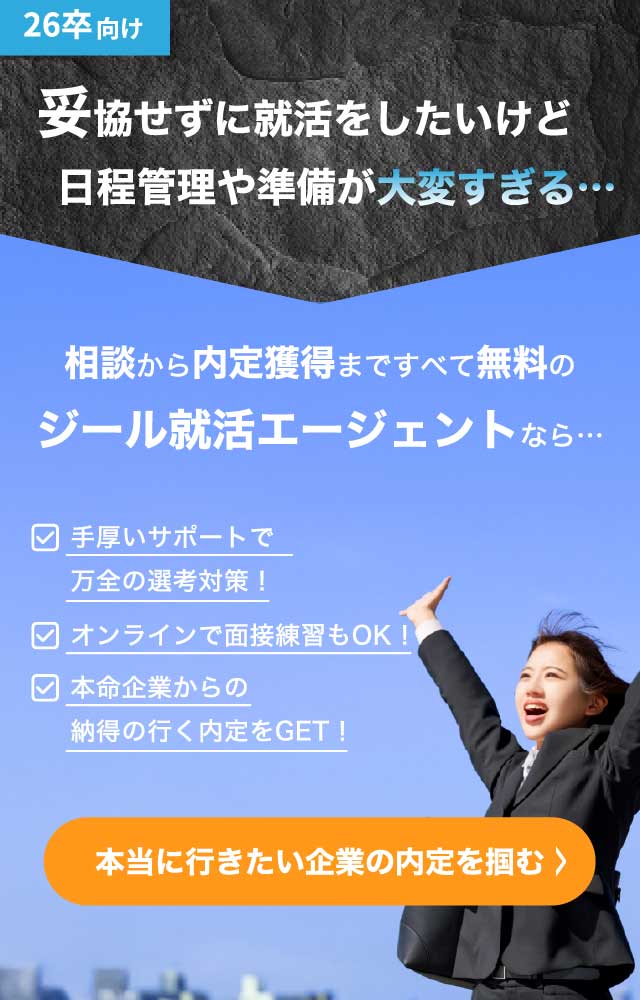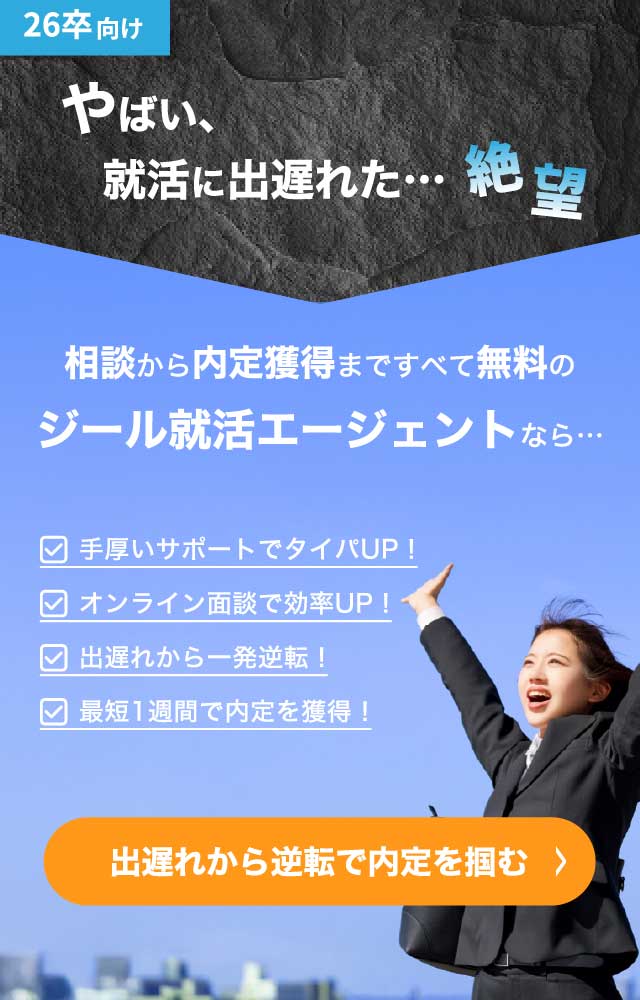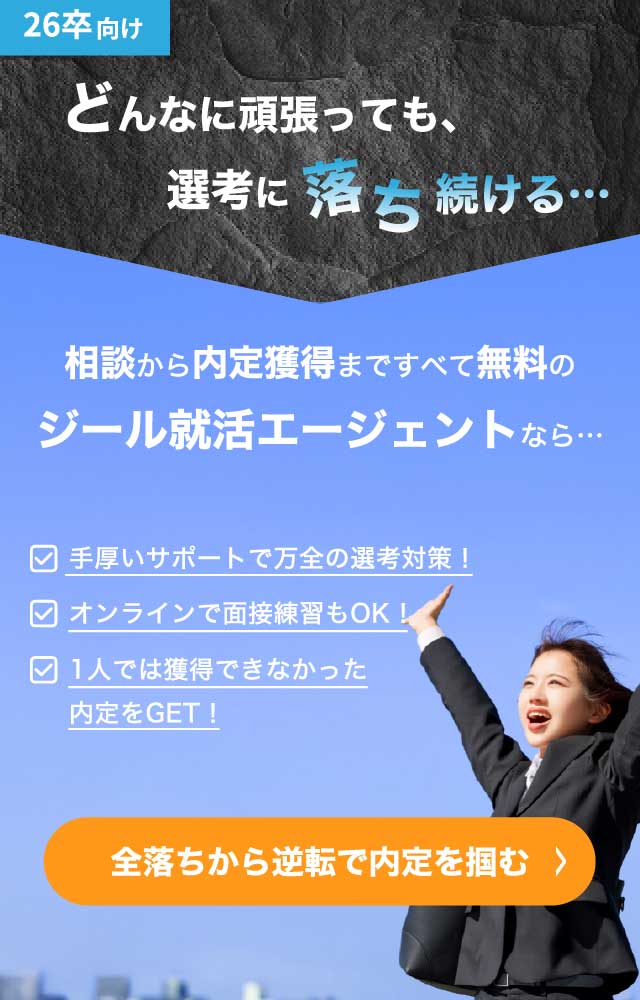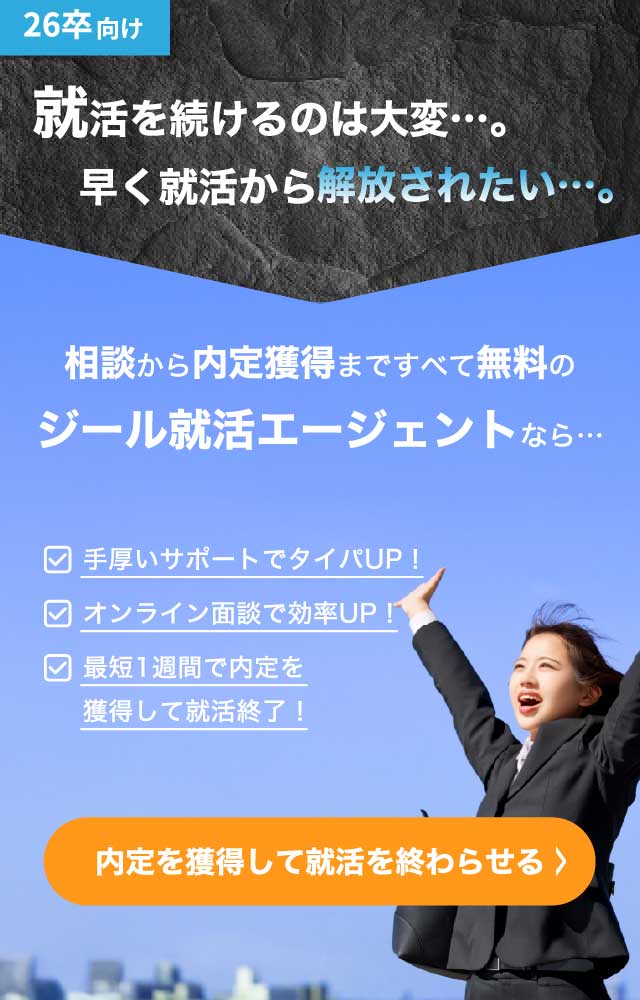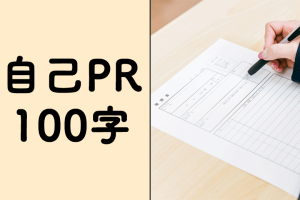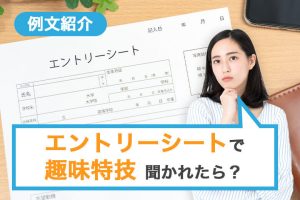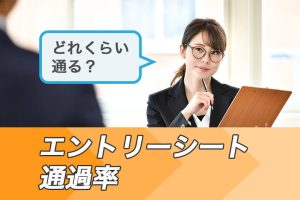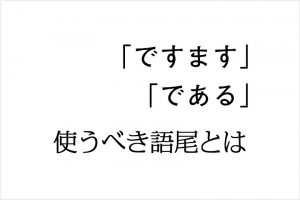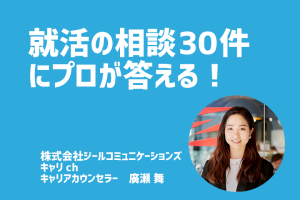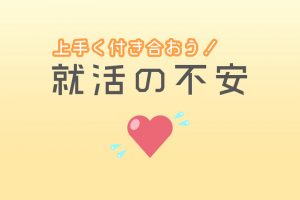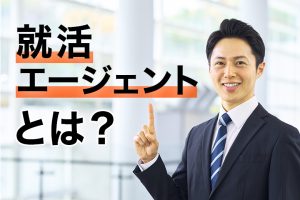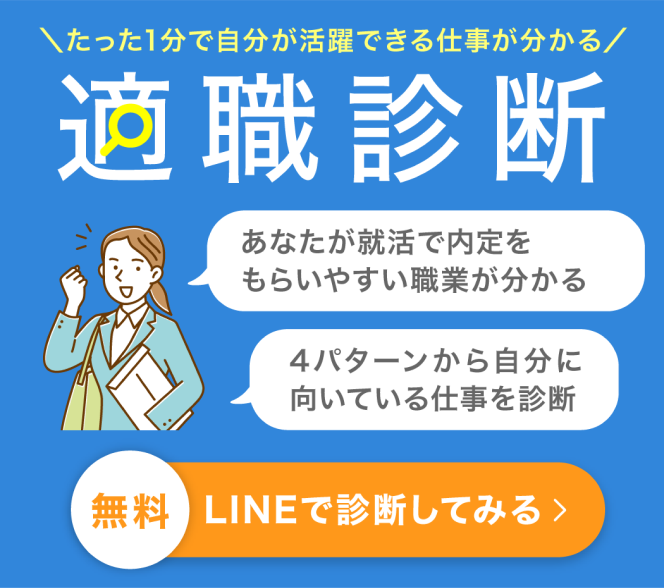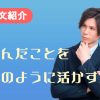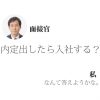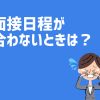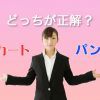就活生向けES作成方法|準備から通過率UPのポイント・書き方
2025年10月10日

エントリーシートって、どこまで書き込めばいいのか分からなくて…。自己PRとか志望動機とか、正直どう書いたら通るのか不安なんです。
そうですよね。ESは就活の最初の関門ですが、書き方のコツを押さえるとグッと通過率が上がりますよ。実は、伝え方にはちょっとした「型」や工夫があるんです。


知らずに感覚で書いてました…。テンプレとかもあるなら知っておきたいです。
もちろん、自己PRや志望動機のテンプレート例、企業がチェックしているポイント、さらにはAI添削などの効率的な方法もあるので、就活の成功につながるESを作成できるようになるために解説していきましょう。

ESの役割
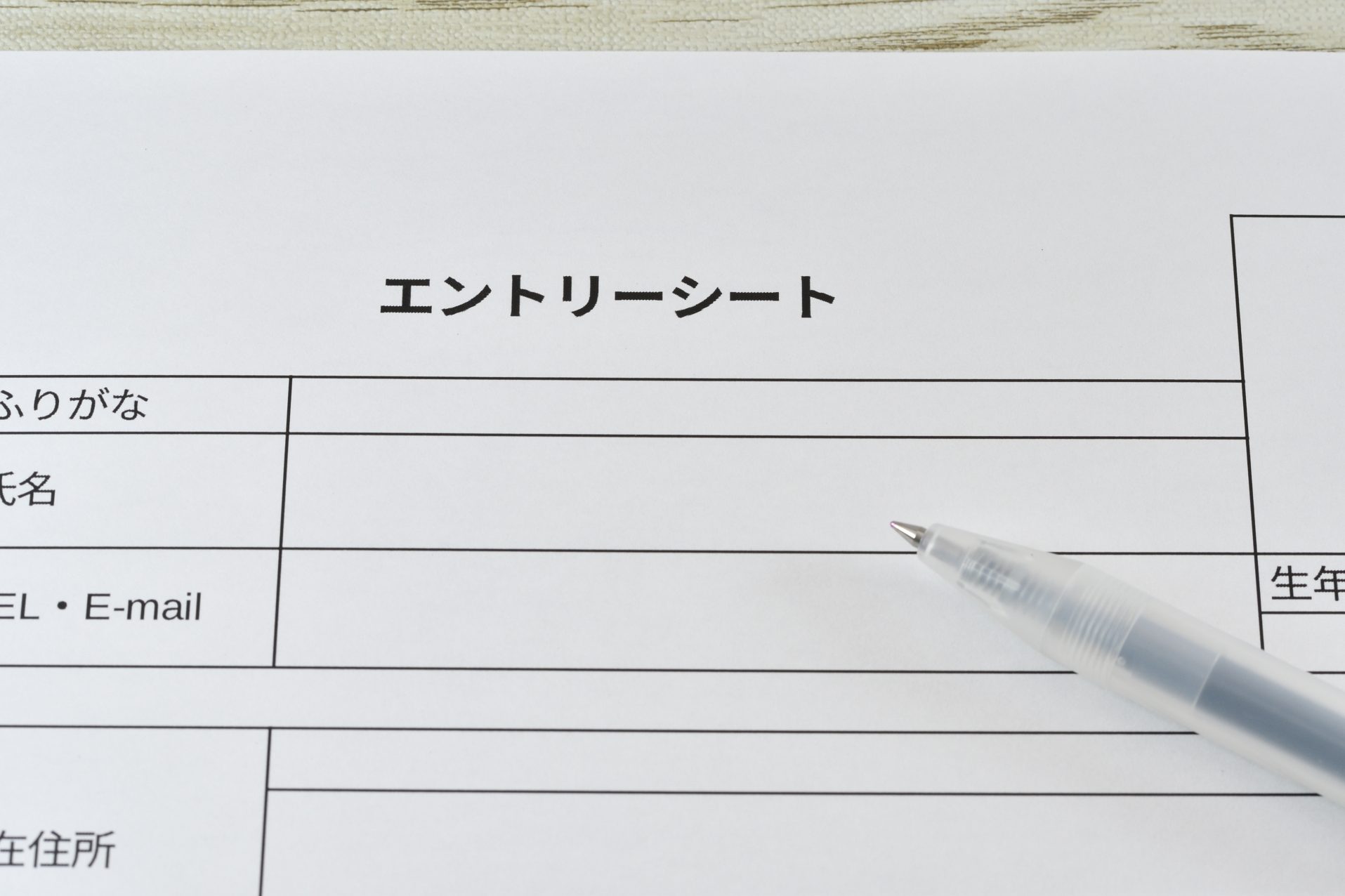
ここでは、ES(エントリーシート)が就職活動全体の中でどのような意味を持ち、どのように活用されているのかを解説します。選考の第一関門としての重要性や、履歴書との具体的な違い、企業がチェックする視点について知ることで、より効果的に準備することが可能です。
ここで解説する内容を読むことで、ESに求められる意味や重要性を理解できるでしょう。
以下コラムでは、ES対策について解説しているので、あわせて参考にしてください。
関連コラム
エントリーシート対策はこれでOK!内定に結び付くES講座
就活におけるESの位置づけとは
就活においてESは、就職活動における第一関門として大きな役割を果たしています。
なぜなら、多くの企業がESの内容をもとに面接へ進めるかを決定するからです。たとえば、志望動機や自己PRがしっかり書かれている学生は、面接官に意欲や熱意が伝わりやすく、次の選考に進みやすいでしょう。
さらに、ESは選考を通じて面接官が質問を組み立てるための資料としても活用されます。
書き方や内容次第で面接時の印象にも影響するのが特徴です。ESは単なる書類ではなく、選考全体の方向性を左右する重要なツールであると認識しましょう。
履歴書とESの違い
履歴書とESは似た書類のように感じられますが、実際には役割や評価のされ方に大きな違いがあります。
違いは、下記の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 履歴書 | 学歴や資格など客観的な経歴確認に重点を置く |
| ES | 応募者の人柄や考え方、志望度を評価するために活用される |
例として、履歴書は決められたフォーマットに沿って記載する一方で、ESは設問に応じて自由記述を求められるケースが多いでしょう。さらに、企業ごとに設問やフォーマットが異なるため、求められる内容もさまざまです。
履歴書と同じ感覚で記入すると不十分になりがちなので、それぞれの違いを理解して準備する必要があります。
企業がESで見ている観点
企業はESを通して、下記がバランスよく備わっているかを確認しています。
- 人柄
- スキル
- 志望度
- 企業理解
なぜなら、上記の要素が全体的に高いレベルでまとまっている応募者は、入社後の活躍が期待できるからです。
たとえば、自己PR欄でこれまでの経験や強みを具体的に示し、志望動機で業界や企業の理解をしっかりと書いているESは、高評価を得やすいでしょう。
一方で、どれかひとつに偏った内容は全体の印象を悪くしてしまうこともあるため注意が必要です。4つの観点を意識して、読み手に伝わりやすいバランスの良いESを仕上げましょう。
以下コラムでは、人事の目に留まりやすいESの書き方について解説しているので、あわせて参考にしてください。
就活でES作成の準備を始めるタイミング

ここでは、就職活動においてESの準備を始める最適な時期や、効率よく進めるために押さえるべきポイントを解説します。業界ごとの提出時期の目安、準備段階でやるべき作業、出遅れてしまった場合の対応策まで把握することで、安心して書き始められるでしょう。
ここで紹介する内容を参考に、効果的な準備を進めるためにお役立てください。
ESの提出時期と準備期間
ESの提出時期は、業界や企業によって大きく異なりますが、準備は少なくとも3か月前から始めるのが望ましいでしょう。
なぜなら、業界ごとに選考開始のタイミングが異なり、想定より早まることもあるためです。
たとえば、外資系やマスコミ業界では前年の年末から選考が動き出すケースがある一方で、メーカーやインフラ系は春先が中心になるでしょう。さらに、複数社への応募を視野に入れると、提出するESの数が一気に増えるため、余裕をもって作業を進める必要があります。
準備期間をしっかり確保しておけば、修正や添削の時間も取れるため、完成度を高めやすいでしょう。結果として、計画的な準備が選考通過率を高めるポイントになります。
ES作成の準備でやるべきこと
ESの作成準備では、下記の3本柱にしっかり取り組むことが欠かせません。
- 自己分析
- 企業研究
- 文章練習
理由は、事前に準備を整えることで文章の一貫性が生まれ、読み手に伝わる内容になるからです。
例として、自己分析では自分の強みや経験を言語化し、どのように企業に貢献できるかを明確にします。加えて、企業研究によって業界の動向や企業の特徴を深く理解し、志望動機に説得力を持たせることも大切です。
結果として、提出時に自信を持って仕上げられるESが完成します。
ES作成に出遅れた場合の巻き返し法
万が一、ESの準備に出遅れてしまった場合は、テンプレート活用やAI支援、短期集中の戦略で巻き返すことができます。
なぜなら、近年は効率的に作成できる便利なツールやノウハウが充実しているためです。
例として、自己PRや志望動機の構成テンプレートや過去の例文を参考にしながら素早く形にする方法があります。さらに、AI添削ツールを活用すれば文章の改善点がすぐに分かり、短時間で質の高い内容にブラッシュアップできるでしょう。
加えて、自己分析や企業研究も必要最小限に絞り込み、優先順位を付けることで時間を有効に使えます。結果として、時間が限られていても一定以上の完成度を持つESを提出できるようになります。
あわせて、キャリチャンの「出遅れ就活サポート」も活用するとよいでしょう。ES作成に出遅れてしまった場合の巻き返しをサポートします。
ESの土台づくりに重要な自己分析と企業研究

ここでは、ESの質を高めるために欠かせない自己分析と企業研究の具体的な進め方を解説します。簡単に実践できる自己分析の方法や、企業研究を深めるポイントを押さえることで、説得力のあるESを作成する土台を整えることが可能です。
ここで解説する内容を読むことで、選考を突破するための準備がしっかり整えられるでしょう。
また、キャリチャンで提供している自己分析ワークシートもぜひ利用してみてください。自己分析が必要なワケや、わかりやすい自己分析のやり方を記載してるだけでなく、実際に作成することも可能です。
【就活対策資料】
自己分析ワークシート
簡単にできる自己分析の方法
自己分析は、ESに説得力のある自己PRや志望動機を書くうえで重要なポイントといえます。
なぜなら、自分の価値観や強みを明確にすることで、文章に一貫性が生まれるからです。
たとえば、下記を具体的に書き出しましょう。
- いつ(When)
- どこで(Where)
- 誰と(Who)
- 何を(What)
- なぜ(Why)
- どうしたのか(How)
5W1Hの視点で過去の経験を振り返ることで、自分の行動や考え方の傾向が見えてきます。さらに、モチベーショングラフを作成すると、やる気の高まる場面や苦手な状況が可視化できるでしょう。
また、価値観診断ツールを活用すれば、自分では気づかなかった強みや適性を客観的に知る手がかりになります。結果として、先述した方法を組み合わせると短期間でも自分らしさが伝わる材料をそろえることが可能です。
企業研究の進め方
企業研究は、志望動機や企業理解の深さを伝えるために欠かせない準備といえます。
理由は、相手のことをしっかり知るほどに説得力のある文章が書けるようになるからです。
例として、事業内容や主力商品、社風や理念について調べ、自分の価値観や志向とどのように合うかを考えることが挙げられます。さらに、職種ごとの業務内容も把握しておくと、より具体的な志望理由につながるでしょう。
調べる手段としては、企業ホームページの採用情報やIR資料に加え、先輩社員の声や就活イベントで得られるリアルな情報も役立ちます。結果として、企業の特徴に合わせて的確にアピールできるESが書けるでしょう。
就活のES作成で役立つ自己PRの書き方

ここでは、ESでしっかり評価される自己PRの書き方について詳しく解説します。アピールポイントの選び方や、説得力を高める構成の工夫、避けたいNG例と改善のコツまで押さえることで、伝わる文章が書けるようになるでしょう。
ここで紹介する内容を参考に、強みが伝わる自己PRの準備にお役立てください
あわせて、キャリチャンの「就活相談サポート」もおすすめです。自己PRの書き方や面接の立ち回りなど、キャリチャンがご紹介する企業に合わせた具体的なアドバイスをご用意しています。あなたに合った選考対策を、一緒に進めていきましょう。
アピールポイントの選び方
自己PRでは、自分の強みを適切に選び、企業との接点を意識することが求められます。
なぜなら、どんなに優れた強みでも、企業が求める人物像とズレていると評価されにくいからです。
たとえば、まずは自己分析で過去の経験や周囲からの評価をもとに、強みの棚卸しを行いましょう。そのうえで、応募する企業が重視している価値観や求めるスキルと重なる要素を選ぶと、説得力が増します。
また、業界や職種に応じて強調するポイントを調整するとより効果的でしょう。結果として、伝えたい強みが企業のニーズに合致する自己PRに仕上がります。
エピソードの構成法
自己PRを書く際は、結論→根拠→行動→成果の順で構成するのが効果的といえます。
理由は、読み手に強みが明確に伝わり、説得力が増すからです。
例としては、「私は課題解決力に自信があります」と結論から入り、次に「アルバイト先で売上が落ち込んだ際に改善案を考えました」と背景や理由を説明します。
さらに「実際に顧客アンケートを実施し、改善策を提案して実行した」など具体的な行動を書き、最後に「結果、前年比で売上が20%増加しました」と成果を数字で示すと良いでしょう。
結果として、論理的かつ具体的な自己PRに仕上がります。
以下コラムでは、ESの効果的な書き方と例文について解説しているので、あわせて参考にしてください。
関連コラム
エントリーシートの自己PR|就活で効果的な書き方と例文を紹介
よくあるNG例と改善策
自己PRでよく見られる失敗として、抽象的な表現や努力自慢、無駄に長い文章が挙げられます。
なぜなら、読み手に強みが伝わりづらく、印象に残らないからです。
たとえば、下記のような抽象的な文章だけではどのような強みなのか判断できません。
- 私は頑張る人間です
- 一生懸命努力しました
さらに、冗長的な文章は読み手に負担を与えてしまうでしょう。
改善策としては、強みを具体化し、根拠やエピソードを簡潔にまとめることです。加えて、結論ファーストを意識し、定量的な成果や第三者の評価を補足すると説得力が増します。結果として、伝えたいポイントが鮮明で読みやすい自己PRが完成するでしょう。
また、キャリチャンで提供している履歴書・ES作成マニュアルもぜひ利用してみてください。書き方を丁寧に解説しているだけでなく、過去のインターン志願者の例文も複数掲載しているので、より具体的なポイントが把握できるでしょう。
【就活対策資料】
履歴書・ES作成マニュアル
就活のESで効果を発揮する志望動機
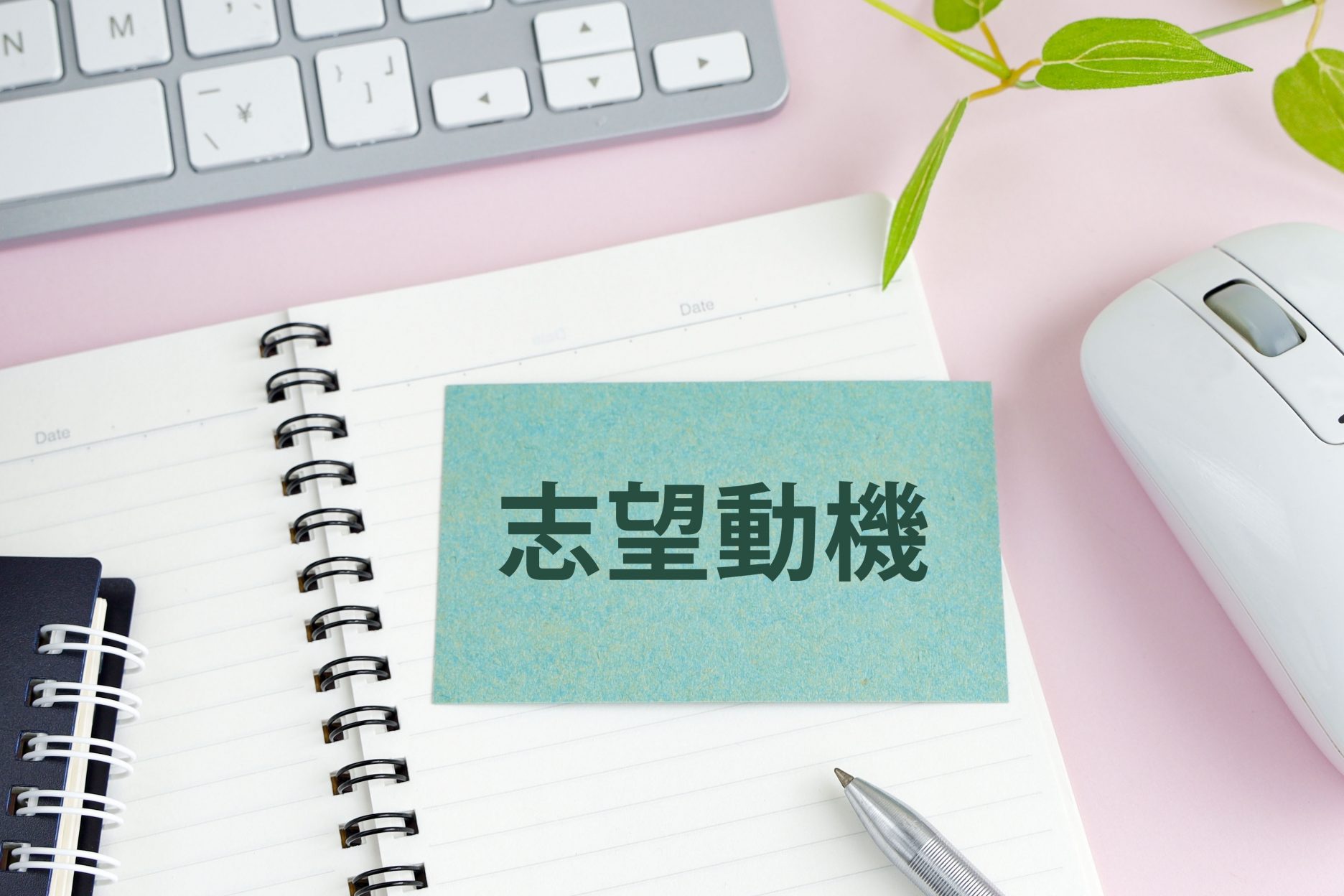
ここでは、ESでしっかりと評価される志望動機の書き方について詳しく解説します。基本ステップを押さえた構成の仕方や、企業理解を盛り込む工夫、さらにありがちな文章を避けるためのポイントまで知ることで、印象に残る志望動機を作ることが可能です。
ここで解説する内容を読むことで、採用担当者の心に響く志望動機が書けるようになるでしょう。
以下コラムでは、ESでの志望動機の書き方について解説しているので、あわせて参考にしてください。
関連コラム
エントリーシートでの志望動機はこう書く!就活のプロが教えるESの書き方
志望動機を構成する基本ステップ
志望動機は、下記の流れで構成すると論理的で伝わりやすいでしょう。
- やりたいこと
- 原体験
- 企業選定理由
- 入社後の目標
なぜなら、やりたいことだけでは説得力に欠けますが、そこに原体験や具体的な背景を加えることで、一貫性が生まれるからです。
たとえば「私は人の生活を支える仕事がしたいと考えています」と結論を示し、その後「幼少期に親が介護職として働いていた姿に影響を受けた経験があります」と原体験を説明します。
さらに「その理念に共感し、御社が掲げる高齢者支援の取り組みを理解し選びました」と企業選定理由を続けると効果的です。
最後に「入社後は現場で経験を積み、マネジメントにも挑戦したい」と目標を添えると完成度が高まります。結果として、読み手が納得しやすい流れになるでしょう。
志望動機に企業理解を盛り込むコツ
志望動機に説得力を持たせるには、企業理解をしっかり盛り込むことが重要といえます。
理由は「なぜこの企業か」が明確でなければ他社にも通じる内容になり、評価されにくくなるからです。
例としては、事業内容や理念、社風の中から、自分の価値観や経験ととくに重なる部分を具体的に示します。
たとえば「御社の『地域に根ざした医療』という理念に共感し、ボランティア活動で得た経験が活かせると感じました」と書くとよいでしょう。
さらに、他社の類似事業ではなく、その企業独自の特徴や強みについて触れると差別化ができます。結果として、企業研究の深さが伝わる志望動機に仕上がるでしょう。
ありきたりな志望動機を避けるポイント
ありがちな志望動機を避けるためには、自分だけの視点や関心を織り交ぜ、他社との差異に触れることが求められます。
なぜなら「成長したい」「社会に貢献したい」といった表現だけでは、どの応募者も似たような印象になり、埋もれてしまうからです。
たとえば、下記のように自分の背景を絡めて独自性を出すと良いでしょう。
<自分の背景を絡めて独自性を出す例文>
御社の●●事業の中でも、とくに●●の取り組みが、自分の●●の経験と合致しています。
さらに、競合企業との違いについても一言触れると、調査の深さが伝わります。「同業他社ではなく御社を志望するのは●●が決め手です」と明記すると印象的です。
結果として、他の応募者と差がつき、読み手に記憶されやすい志望動機に仕上がるでしょう。
ESを効率的に作成するための工夫

ここでは、忙しい就職活動の中でも効率よくESを仕上げるための工夫を解説します。使いまわせる文章と調整が必要な箇所の見極め方や、テンプレートを活用した時短術、さらにAIツールを活用することで、無駄を省きながら高品質なESの準備が可能です。
ここで解説する内容を読むことで、時間を有効活用して質の高いESが作れるようになるでしょう。
使いまわせる文章と使い分けが必要な箇所
ESは、項目によって文章の使い回しが可能な部分と、毎回調整が必要な部分があります。
なぜなら、企業ごとに重視するポイントが異なり、全て同じ内容でも伝わり方が変わるためです。たとえば、ガクチカや自己PRは、エピソードの軸さえ決まっていれば全体の7割ほどは共通して使いまわせるでしょう。
一方で、志望動機や企業名は毎回の調整が欠かせません。理由は、その企業独自の事業や理念、強みと応募者の関係性を示す必要があるからです。
加えて、社風や事業への共感を具体的に記載するためには、都度企業研究の情報を反映させるとよいでしょう。結果として、効率よく書きつつも独自性を失わないESになります。
テンプレートを活用した時短術
効率よくESを仕上げるには、構成テンプレートを活用すると時短になります。
理由は、ゼロから文章の流れを考える時間を減らし、伝わりやすい型に沿って書けるからです。例としては、PREP法や結論ファースト型をあらかじめ決めておくと、読みやすくまとまった文章になります。
たとえば、下記の流れを意識するだけでも、内容が論理的で一貫した文章になるでしょう。
- 結論
- 理由
- 具体例
- まとめ
加えて、企業研究のメモや自己分析結果をテンプレートに組み込んでおけば、各社向けに微調整するだけで済みます。
結果として、無理なく時短が実現し、提出するまでの負担も軽減できるでしょう。
以下コラムでは、PREP法について解説しているので、あわせて参考にしてください。
関連コラム
【例文】就活で使えるPREP法とは?自己PRの書き方を解説!
AIによるES添削・自動生成ツールの活用
忙しい就活生にとって、AIを活用したES添削や自動生成ツールは非常に効果的といえます。
なぜなら、短時間で文章の問題点を指摘してくれたり、構成案を提示してくれたりするため、効率が大幅に向上するからです。たとえば、AIに文章を入力するだけで言い回しの改善案や冗長的な部分が見つかり、すぐにブラッシュアップが可能になります。
<AIに入れるプロンプトの例文>
あなたは(企業名)の人事です。
以下のテキストを、思わず採用したくなるようなエントリーシートの内容に書き換えてください。
""
~確認したい文言を貼り付ける~
""
ただし、AIの提案をそのまま採用するのではなく、必ず自分の目で確認し、内容の整合性やオリジナリティを保つ意識が求められます。結果として、時短しながらも質の高いESが仕上がるでしょう。
ESの提出戦略と通過率を上げる戦略

ここでは、効率的にESを提出し、選考を有利に進めるための戦略を詳しく解説します。通過率の高いESに共通する特徴や、提出数と応募先のバランス、さらに通過しやすい企業の傾向を知ることで、計画的に就活を進めやすくなるでしょう。
ここで紹介する内容を参考に、戦略的にESを準備して提出するためにお役立てください。
ESの提出戦略を相談したい方には、キャリチャンの就活支援サービス「就活相談サポート」がおすすめです。自己PRや面接対策など、キャリチャンがご紹介する企業ごとに最適化したアドバイスをお届けします。無駄のない準備で、内定への一歩を確実にしましょう。
通過率の高いESに共通する特徴
通過率の高いESには、端的で具体的かつストーリー性のある文章という共通点があります。
なぜなら、読み手が理解しやすく印象に残る内容こそが選考で評価されやすいからです。たとえば、長々と抽象的な文章よりも、結論を先に書き、具体的なエピソードや成果を盛り込むと説得力が増します。さらに、業界や職種に適した語彙を使い、評価する側が判断しやすい構成に整えるのもポイントです。
一方で、複雑すぎる表現や過剰な修飾語は読みづらさにつながるため、避けるべきでしょう。結果として、シンプルながらも印象に残るESに仕上がり、通過率が高まります。
ES提出数の目安と戦略
ESの提出数は、下記の3つに分けてバランスよく決めるのが賢明でしょう。
- 第一志望群
- 滑り止め
- 練習用
理由は、最初から本命企業だけに絞ると経験不足で失敗しやすく、反対に出しすぎると質が落ちるためです。たとえば、最初は練習用として選考が早めの企業にいくつか応募し、フィードバックや感触を得ると本番に活かしやすいでしょう。
もちろん、第一志望群は企業研究やESの精度を高めて準備するのが重要です。加えて、落ちる前提の挑戦も織り込みつつ提出先を決めると、計画的に就活を進めやすくなります。結果として、無理のない範囲で高い完成度を保ちながら、多くの選考に挑めるでしょう。
通過しやすい企業の傾向
通過しやすい企業には、文系・理系や大手・ベンチャーによる評価基準の違いがあります。
なぜなら、企業によって重視する要素が異なり、判断基準に合致する学生が選ばれやすいからです。たとえば、理系では専門知識や研究内容の具体性が重視され、文系では課題解決力や対人スキルが評価される傾向があります。
さらに、大手は文章力や論理性を重視する一方で、ベンチャーは行動力や挑戦心に注目する場合が多いでしょう。結果として、提出を重ねるごとにデータが蓄積され、戦略的に動けるようになります。
ES提出前の最終チェック項目

ここでは、ESを提出する直前に確認すべき重要なポイントを解説します。文章やレイアウトの見え方、誤字や表現の正しさ、そして提出方法やマナーまでしっかり確認することで、細部まで行き届いた高品質なESが仕上がるでしょう。
ここで紹介する内容を参考に、最後の仕上げで印象をさらに良くしてください。
文章とレイアウトを確認する
提出前には、文章の内容だけでなくレイアウトや見た目まで確認するとよいでしょう。
なぜなら、読みやすく整ったESは読み手に好印象を与えるからです。たとえば、フォントや文字サイズ、文字数のルールが企業指定に沿っているか見直しましょう。
さらに、文末表現が統一されているかも重要で「です・ます」や「〜しました・〜しました」の繰り返しにならないよう工夫してください。加えて、空欄や余白が不自然に多く残っていないかもチェックが必要です。結果として、内容だけでなく見た目まで配慮されたESに仕上がり、完成度が高まります。
誤字・脱字・略語を排除する
ESに誤字や脱字、略語が残っていると、それだけで評価が下がる可能性があります。
理由は、基本的なビジネスマナーや文章力が不足していると受け取られるためです。
たとえば「バイト」「コンビニ」などの略語は避け、「アルバイト」「コンビニエンスストア」と正式な表現に直しましょう。さらに「やばい」「すごい」などの口語的な言い回しも避け、丁寧語や適切な語彙に置き換えるのが基本です。
加えて、誤字脱字がないかは必ず複数回確認し、可能であれば第三者に読んでもらうと安心でしょう。結果として、読み手に伝わりやすいESが完成します。
提出方法とマナーを改めて把握する
提出方法やマナーを守ることは、内容以上に重要視される場合もあります。なぜなら、締切や手順を守れるかどうかは社会人としての基本姿勢が問われる部分だからです。
たとえば、手書きかWeb入力か提出形式を事前に確認し、企業の指定に沿って準備しましょう。さらに、締切日時もギリギリの提出ではなく、厳守したうえで余裕を持って提出する姿勢が望ましいです。
加えて、Web提出の場合はファイル名にも配慮し「エントリーシート_氏名.pdf」のようにわかりやすい形式に整えてください。結果として、形式やマナーまで含めて整った提出ができ、担当者に良い印象を残せます。
通過率を高めるESの書き方と対策
就職活動においてESは、面接へ進むための重要な第一関門です。通過率を高めるには、基本を押さえつつ戦略的に準備を進めることが欠かせません。自己分析や企業研究を徹底し、自分の強みや志向と企業の特徴が一致するポイントを見つけると、説得力のある自己PRや志望動機が書けるでしょう。
ガクチカや自己PRは汎用的に使い回しつつ、志望動機は各社に合わせて調整する工夫が必要です。文章は結論ファーストで具体性とストーリー性を持たせ、読み手が理解しやすい構成に整えると高評価が期待できます。
さらに、提出前には誤字や略語、マナーまで確認し、企業ごとの提出方法や締切を守る意識も重要です。対策を重ねることで、完成度の高いESとなり、選考を有利に進められるでしょう。
「就活相談サポート」に参加しよう!
この記事の監修者

平崎 泰典
株式会社ジールコミュニケーションズ
HR事業部マネージャー
2016年に入社後、企業向けの採用コンサルティング業務を経て、就職・転職希望者に対する個別就職支援を担当。「キャリチャン」「合説どっとこむ」において年間100回以上の就職・転職セミナーの講師も務める。
主な担当講座に「営業職や種類が適性がよくわかる解説講座」「手に職をつけられる仕事解説講座」などがあり、これまで3,000名以上に対して講座を実施。
就職支援では「自己分析」と「業界研究」を得意として、就活初期の学生や求職者を相手に基礎からサポートを行う。年間1,000名以上の内定獲得を支援。