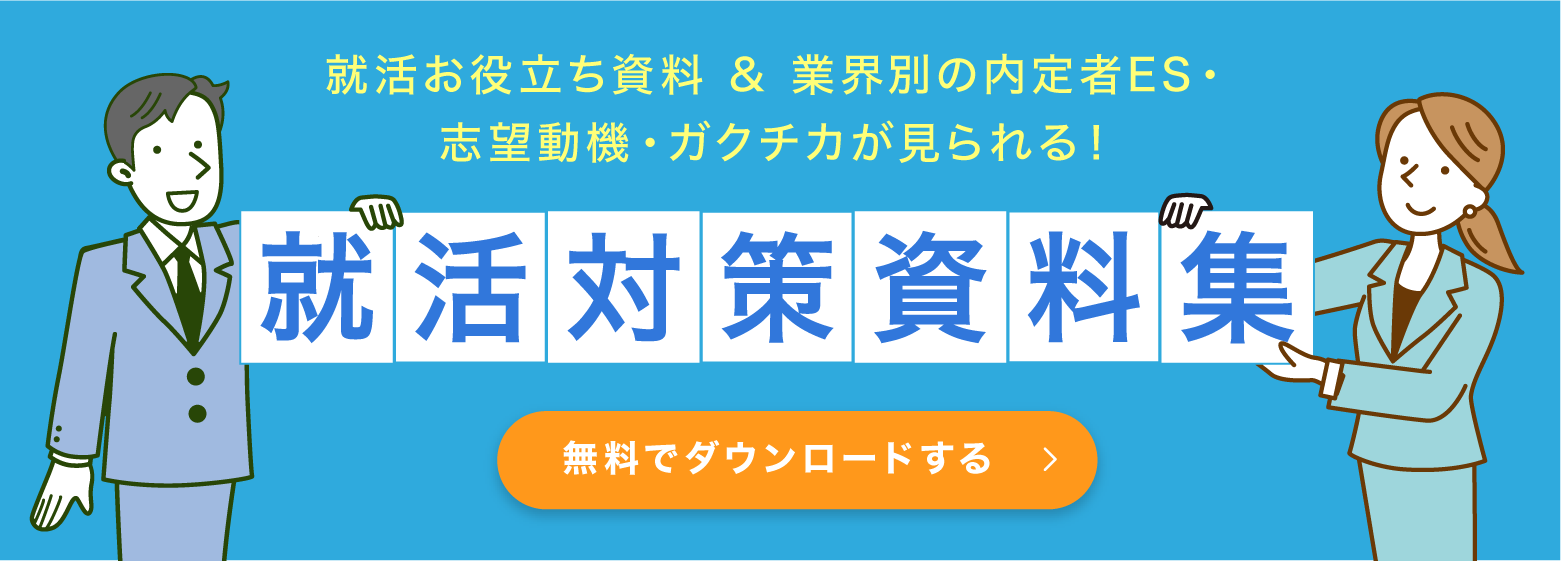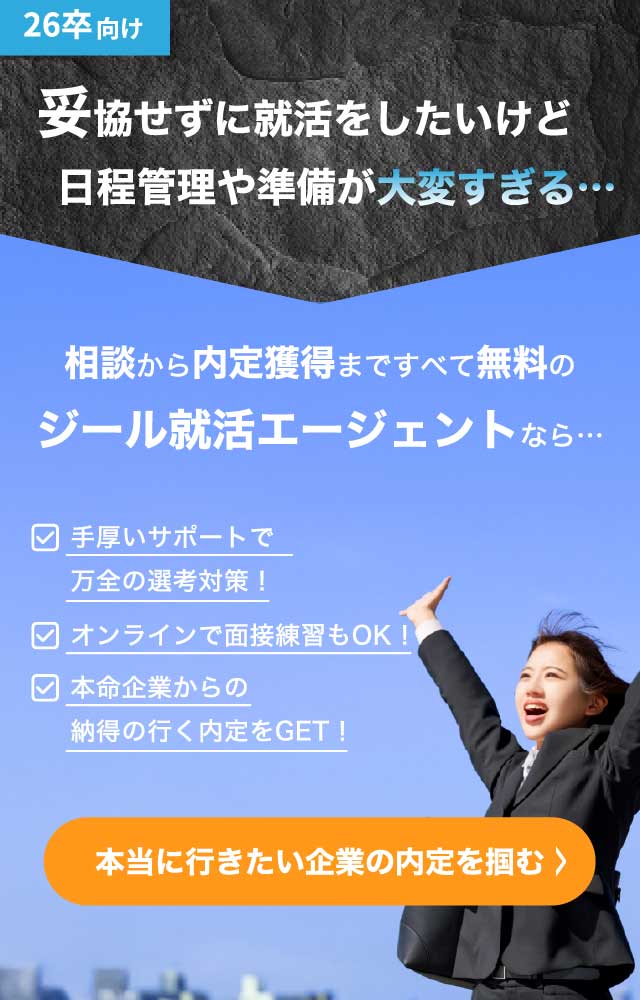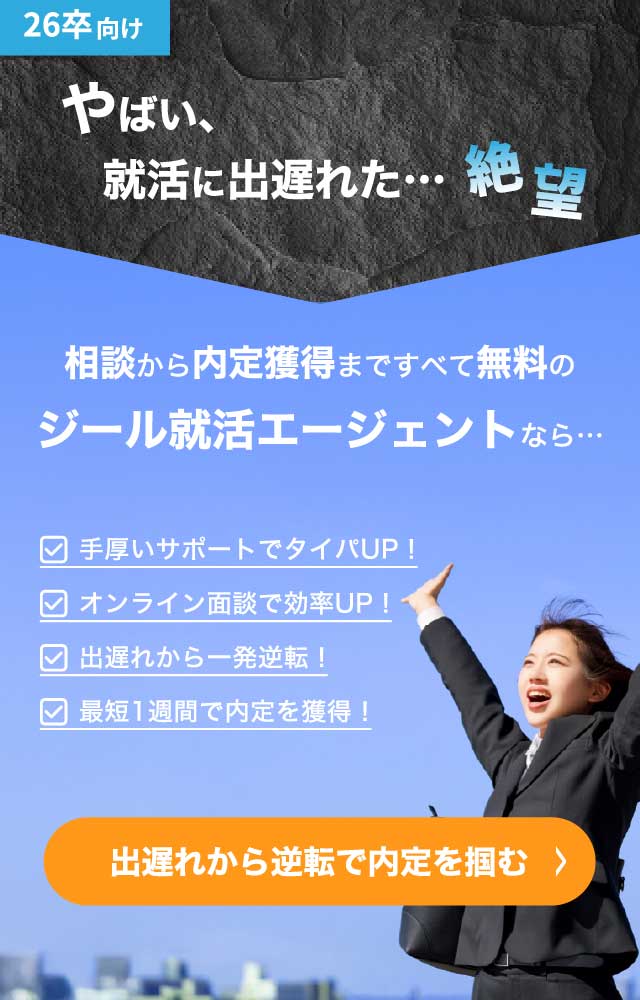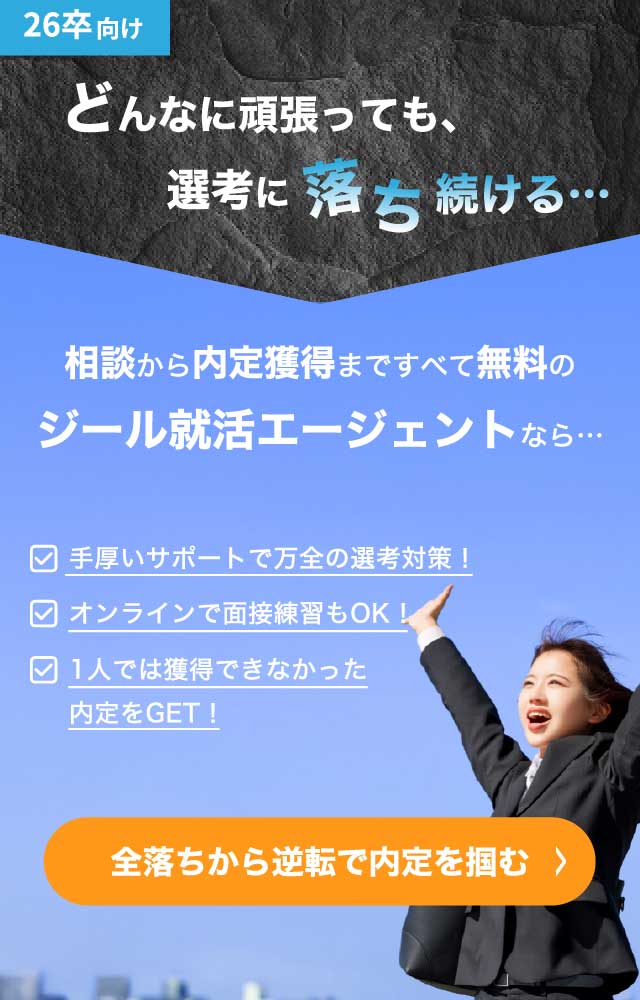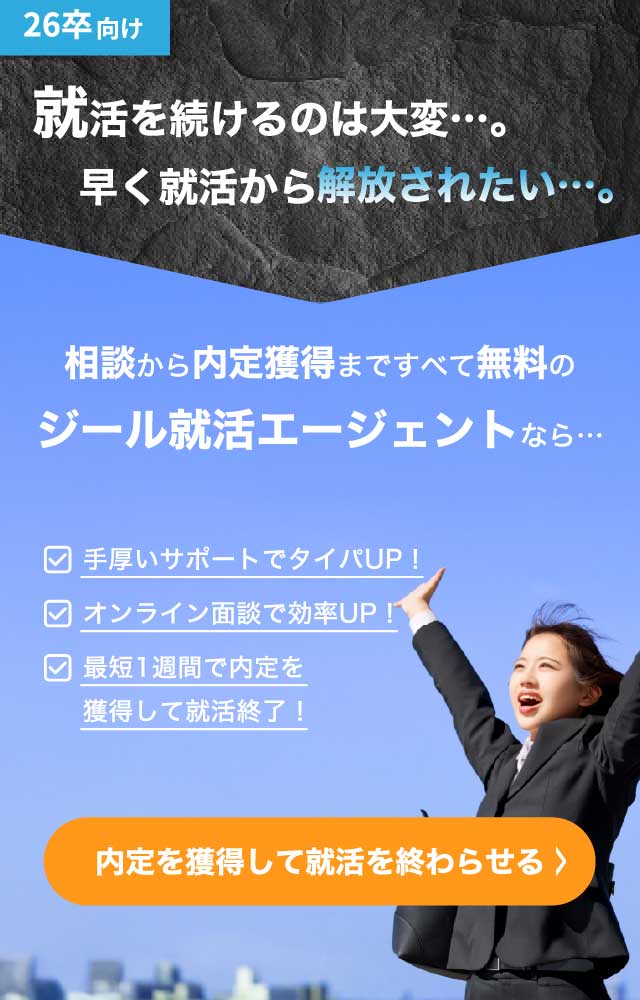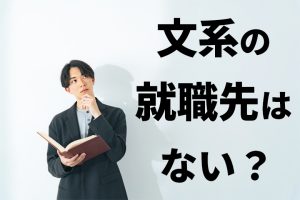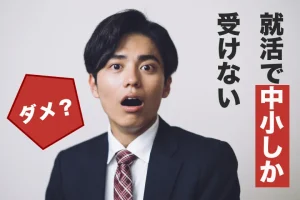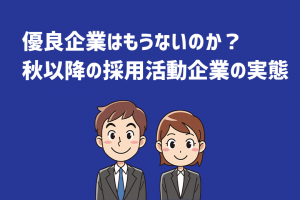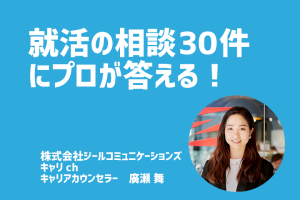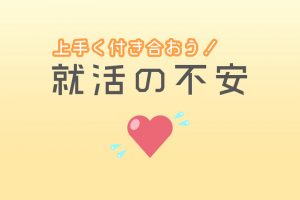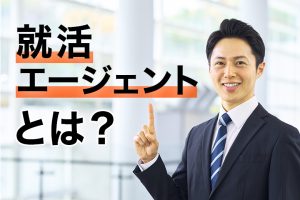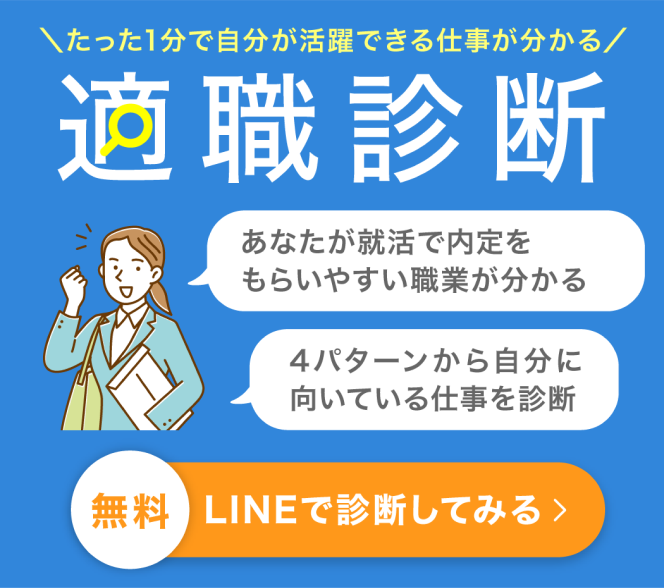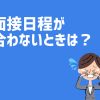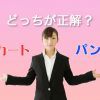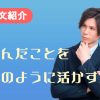残業が多い業界はどこ?| 長時間残業による懸念や効果も解説
2026年2月3日
 就活生 Aさん
就活生 Aさん
これから就活をするうえで、どの業界で残業時間がの多いのか知っておきたいです。
それはどうしてでしょうか?残業が多い業界で働くと、健康面やメンタル面への影響が心配だからですか?
 キャリアアドバイザー 廣瀬
キャリアアドバイザー 廣瀬
 就活生 Aさん
就活生 Aさん
そうなんです。あとは仕事も大事ですけどプライベートも大事なので、残業時間が多い業界や企業を避けた方がいいのかなって思ってます…。
わかりました。では今回は、残業が多い傾向にある具体的な業界や、その特徴について紹介します。残業時間がもたらすメリット・デメリットも解説するので、参考にしてください。
 キャリアアドバイザー 廣瀬
キャリアアドバイザー 廣瀬
残業が多いと言われている主な業界

残業が多いと言われている代表的な業界は、大きく分けて以下の5つです。
ここでは、上記の業界が残業が多いと言われている背景を詳しく解説します。ここで紹介する内容を把握することで、就活の時にどの業界を志望するか決める判断材料を得られるでしょう。
残業については、就活の面接で聞くことも可能です。面接での対応について詳しく知りたい人は、以下のコラムもあわせてチェックしてみましょう。
関連コラム
面接で「残業」について答える方法と逆質問で上手に聞き出すコツを解説
なお、残業時間の少ない業界に就職したいなどの相談は、キャリチャンの就活支援サービス「就活相談サポート」でも対応可能です。残業が少ない業界の求人紹介も行っているので、ぜひ利用を検討ください。
IT・システム開発業界
残業が多いと言われている主な業界の1つに、IT・システム開発業界があります。
IT・システム開発業界では、納期や仕様変更、トラブル対応などで急ぎのタスクが発生することがあり、その影響で残業が発生しやすい傾向があります。
プロジェクトの進行には多くの変数が絡み、予定通りに進まないことが少なくありません。そのため、納期前の追い込みや頻繁な仕様変更、システム障害対応が発生し、その結果、残業時間が増えがちです。
たとえば、開発現場ではリリース直前に急な仕様変更が発生し、作業量が大幅に増加することがあります。クライアントの要望に対応するため、長時間労働が避けられない場面もあるでしょう。加えて、システム障害やサーバートラブルが発生した場合、夜間や休日であっても即座に対応しなければなりません。
IT業界で働くには、プロジェクトの進行管理や仕様変更への対応力が求められます。長時間労働を避けるためには、職場の業務フローや労働環境をしっかり確認することが大切です。
コンサルティング業界
コンサルティング業界も、残業が多いと言われる業界の1つです。
なぜなら、コンサルティング業界は、クライアント対応や膨大な資料作成、徹底的なリサーチ、頻繁な出張など長時間労働の要因となる業務が多く含まれるからです。
顧客からの急な依頼が発生した場合、その対応を優先する必要があり、業務計画の変更が発生します。また、提案書やプレゼン資料の作成には時間を要し、夜遅くまで作業が続くこともあるでしょう。出張やクライアントとの長時間の会議も多く、移動時間を含めるとさらに労働時間が増加していきます。
コンサルティング業界では、高い業務負荷とクライアント対応の柔軟性が求められます。業務効率化の工夫や労働環境を重視した企業選びが、長時間労働を回避するためには欠かせません。
広告・出版・クリエイティブ業界
広告・出版・クリエイティブ業界は、残業が多いと言われています。
広告・出版・クリエイティブ業界では、納期の厳しさや修正対応の多さが、残業時間の増加につながります。
制作スケジュールはタイトであり、締め切りが厳格に設定されているケースがほとんどです。さらに、クライアントの要望によって、完成直前での修正が頻繁に発生することもあります。
広告制作では納期が迫るとスケジュールの圧迫が顕著になり、修正依頼が相次ぐことで業務量が増えがちです。また、クリエイティブな作業はアイデアを形にするまでの時間が読みにくく、計画通りに進まないこともよくあります。その結果、深夜まで作業を続けるケースが多くなることもあるでしょう。
広告・出版・クリエイティブ業界で働く場合は、時間管理スキルが重要となります。企業選びの際には、労働環境や業務フローが整備されているか確認しておきましょう。
建築・不動産業界
残業が多いと言われる業界には、建築・不動産業界も含まれます。
なぜなら、建築・不動産業界では、工期を厳守するよう求められている中でも突発的なトラブル対応が発生するなど、長時間労働が発生しやすい要素があるからです。
たとえば、建設現場では、天候や施工ミスによって進捗に遅れが発生します。その結果、スケジュール通りの進捗に戻すために、夜間や休日にも業務を行うケースが珍しくありません。また、設計・施工・行政手続きなど、多くの関係者との調整業務が発生し、打ち合わせが長時間に及ぶこともあります。
建築・不動産業界では、突発的な業務が発生しやすいため、柔軟な対応が必要不可欠です。就職を検討する際は、企業の労働環境や残業管理の実態をしっかりチェックしておきましょう。
運輸業界
運輸業界も残業が多いと言われる業界の1つです。
運輸業界は慢性的な人手不足と厳しい労働環境によって、残業が多くなりやすくなっています。とくに、長距離輸送や深夜配送などの業務を受け持つと労働時間が長くなりがちです。
運輸業界の長時間労働の背景にあるのは、人手不足です。2019年の労働基準法改正により、時間外労働の上限が厳格化されましたが、運輸業界に関しては特例として5年間の猶予期間が設けられていました。しかし、2024年4月1日からは年間960時間の上限が適用されることになり、業界全体で対応が急務となっています。
また、運輸業界の残業時間は、顧客のニーズによって大きく変動する点も特徴です。遠方への配送がある場合や、夜間や早朝など特定の時間帯に配送しなければならないケースでは、通常の勤務時間を超えて労働することが多くなります。
運輸業界に就職を考える場合は、企業の残業時間の管理や働き方改革への取り組みを確認することが重要でしょう。
残業が発生しやすい業界の特徴

残業が発生しやすい業界には、以下の共通点があります。
ここで紹介する特徴を理解することで、長時間労働になりやすい職場を見極めるヒントを得られるでしょう。
なお、キャリチャンの就活支援サービス「就活相談サポート」では、就業先となる業界の選定も含めたアドバイスを行なっています。残業が多くなりやすい業界の情報はもちろん、残業が発生しにくい業界の求人紹介も実施しているので、ぜひ活用してください。
納期・締め切りに左右される
残業が発生しやすい業界の特徴として、納期や締め切りに左右されることが挙げられます。
納期や締め切りが厳しい業界では、スケジュールの遅れを取り戻すために長時間労働が発生しやすいでしょう。
広告・出版・IT開発業界では、クライアントの指定する納期が絶対であり、遅れが許されません。プロジェクトが予定通りに進まないと、残業せざるを得ない状況になります。
建築・製造業では、工程の遅れが発生すると、納期を守るために追加の作業が発生しがちです。とくに建築業界は天候や資材調達の影響を受けるため、進行が予定より遅れることが少なくありません。
また、IT・システム開発業界ではクライアントの要望が途中で変更されることが多く、追加の開発作業が必要になることが労働時間が増える要因です。
納期に左右される業界では、計画通りに業務を進めることが求められます。外部要因の影響も大きいため、結果として長時間労働が常態化することがあるのです。
クライアント対応が多い
クライアント対応が多いことも、残業が発生しやすい業界の特徴です。
クライアント対応が多い業界は顧客の都合に合わせた業務が発生するため、残業が避けられないケースが多くなります。営業・カスタマーサポート・コンサルタントなどの職種では、顧客対応が営業時間外に及ぶこともあり、労働時間が伸びがちです。
とくにコンサルティング業界では、クライアント向けのプレゼン資料や提案書の作成に多くの時間を要します。広告や不動産業界でも、クライアントの意向に沿った資料作成が求められ、作業量が膨大になるでしょう。
さらに、広告・IT業界では、クライアントからの修正依頼が頻繁に発生し、業務が追加されて残業が発生しやすくなります。
クライアント対応が多い業界は業務のコントロールが難しく、結果として労働時間が長くなるのです。
人手不足が深刻である
残業が発生しやすい業界の特徴には、人手不足が深刻なことも含まれます。
慢性的な人手不足に悩む業界では1人あたりの負担が増え、残業が発生しやすくなります。とくに介護・建設・飲食業界では人材が不足しており、従業員の労働時間が長くなる傾向にあるでしょう。
また、営業・医療・教育業界では過酷な労働環境が原因で離職が相次ぎ、人員補充が追いつかないことが問題となっています。結果、残った従業員の業務負担が増え、長時間労働を余儀なくされるケースが多くなるでしょう。
さらに、医療・警備・運輸業界では、突発的な欠員が発生すると、他の従業員がフォローするために長時間労働を強いられることもあります。
人手不足の業界は労働時間の管理が難しく、残業も常態化しやすいため、就職を検討する際には企業の人員配置や離職率にも注目することが重要です。
企業文化の影響を受けている
企業文化の影響を受けているのも、残業が発生しやすい業界の特徴と言えるでしょう。
企業文化が長時間労働を助長するケースもあります。日本の企業には、勤務時間の長さが努力とみなされる風潮が根強く残っているところもあり、効率的に働いても評価されにくい傾向にあるのです。
また、上司や同僚が遅くまで残業していると、周囲に気を遣って定時で帰りづらい雰囲気が生まれることもあります。とくに、年功序列の文化が強い企業では、「上司より早く帰るのは失礼」といった考え方が根付いてしまいがちです。さらに、紙ベースの作業や不要な会議が多い職場は業務効率が悪く、無駄な残業が発生しやすいでしょう。
こうした文化がある企業では、たとえ制度として残業削減が推進されていたとしても、実態としては長時間労働が続いている場合があります。そのため、就職前に企業の社風や働き方をよく調べることが大切です。
業務管理・働き方改革の遅れがある
残業が発生しやすい業界の特徴として、業務管理・働き方改革が遅れていることが挙げられます。
労働時間の適正管理ができていない企業では、社員の労働時間が見過ごされ、無意識に長時間労働が発生しやすくなります。とくに、上司や人事が労働時間を適切に管理していない場合、業務量が偏り、特定の社員に負担が集中することもあるでしょう。
また、テレワークやフレックス制が導入されていない職場では、決められた時間内に業務を終わらせることが難しく、結果的に長時間働くことになります。さらに、RPAやデジタルツールの活用が進んでいない企業は手作業が多く、業務の効率化が進まないため、業務時間が延びてしまいがちです。
働き方改革が進んでいる企業では、柔軟な勤務制度や業務の効率化が図られており、長時間労働が抑えられる傾向にあります。そのため、企業選びの際には、働き方改革の取り組みが実際に機能しているかを確認することが重要です。
法律・制度の影響を受けている
法律や制度の影響を受けているのも、残業が発生しやすい業界の特徴となっています。
業界によっては、労働基準法の適用が一部緩和されているため、長時間労働が発生しやすい環境があります。たとえば建設・医療・運輸業界では、特例措置があるため、他の業界に比べて労働時間が長くなりがちです。
また、企業によってはサービス残業が横行しているケースもあります。とくに、中小企業では「みなし残業制度」を採用している企業も多く、労働時間が適正に管理されていないことも多いでしょう。
さらに「残業削減」を掲げる企業であっても、業務量自体が減らなければ実質的な労働時間は変わらず、結果として長時間労働が続くのです。
法律や制度の影響を受ける業界では、企業ごとに残業管理の実態が異なります。就職を考える際は、法制度の適用状況や企業の労働環境をよく確認することが大切です。
反対に残業が少ない業界とは?

以下のような特徴を持っている業界は、残業が少ないと考えられます。
ここで紹介する内容は、無理のない働き方ができる企業選びの参考になるでしょう。
残業が少ない傾向にある職種について詳しく知りたい人は、以下のコラムもあわせてチェックしてみましょう。
関連コラム
残業したくない就活生必見!定時退社できる仕事10選
労働時間の管理が徹底されている業界
残業が少ない業界の特徴として、労働時間の管理が徹底されていることが挙げられます。
労働時間が明確に管理されている業界では、長時間労働になりにくい傾向にあります。公務員は労働基準法が厳格に適用され、定時退社が基本となる職場が多いでしょう。とくに地方自治体などでは、残業の発生を抑えるためのルールが整備されています。
金融業界も営業時間が決まっており、業務時間をコントロールしやすい業種です。とくに銀行や保険会社は就業時間よりも営業時間が短く、残務をこなすための時間があらかじめ設けられているので、過度な残業が発生しにくい環境といえます。
メーカーや製造業も、シフト制や生産計画が明確に決められているため、勤務時間が管理されやすいでしょう。
労働時間が厳格に管理されている業界は、働き方の見通しが立てやすいと考えられます。
ワークライフバランスを重視する業界
ワークライフバランスを重視していることも、残業が少ない業界の特徴となっています。
働きやすさを重視する業界では、残業時間が少ない職種が多く見られます。たとえば、ITインフラやネットワークエンジニアはシステムの安定運用が主な業務であるため、障害が発生しない限り定時退社が可能です。
定時退社が可能な業界は過度な労働時間の対策をとっている場合もあり、仮に育児や介護を行なっている場合でも働きやすくワークバランスを保てるでしょう。
また、ワークライフバランスを重視する業界では、育児や介護の必要性が生じた際に時短勤務などの柔軟な働き方が選べる企業が多いです。そのため、ライフステージが変わっても人材が流出しにくく、スキルレベルが保たれることで、残業が発生しにくい環境になっています。
フレックスタイム制・リモートワークが普及している業界
フレックスタイムやリモートワークが導入されている業界では、残業時間が少なくなりやすくなっています。なぜなら、個々人の事情に合わせた柔軟な働き方ができることで、仕事に必要な人手を確保しやすく、業務量を分散できるからです。
IT業界の自社開発企業では、プロジェクトごとの進行管理がしやすく、フレックスタイム制度が整っています。そのため、決まった時間に出社しなくても、自分のペースで働ける環境が整備されているのです。
Webマーケティング業界も、リモートワークが普及している業界に挙げられます。オンラインで業務を進めることが可能であり、通勤による負担がかかりません。残業が少ないとは限りませんが、負担が軽減できるという視点で注目されています。
また、オンライン教育やEラーニング業界では授業やコンテンツ制作のスケジュールを自己管理しやすく、無理なく働くことが可能です。
フレックスタイム制・リモートワークが普及している業界は時間や場所に縛られない働き方ができるため、自分のライフスタイルに合わせた仕事を求める人に適しています。
シフト制・労働時間が明確な業界
シフト制が導入されている業界は勤務時間が厳密に管理されているため、残業が発生しにくい環境が整っていると言えます。
たとえば製造業の工場勤務はライン作業が基本となるため、決められた勤務時間を超えることはあまりありません。
物流センターや倉庫業務もシフト制で業務が管理されているため、残業が発生しにくい業種です。とくに、ピッキングや仕分け作業は、計画的にスケジュールが組まれるため、突発的な業務が少なく、勤務時間が安定しています。
さらに、医療事務は診療時間が決まっており、業務時間のコントロールがしやすいため、定時退社が可能な職種の一つです。
シフト制が採用されている業界は労働時間が明確であり、プライベートの予定も立てやすい点が魅力といえます。
福利厚生が充実し、働き方改革が進んでいる業界
企業の労務管理が徹底され、福利厚生が充実している業界では、無駄な残業が抑えられています。
とくに、大手企業の事務職は労務管理が厳格に行われており、残業が発生しにくい環境が整っているのです。企業によってはノー残業デーを設けるなど、働き方改革が進んでいるケースもあります。
また、研究開発(R&D)の分野はプロジェクトベースの業務が多く、自分のペースで進めやすいのが特徴です。納期の厳しさこそあるものの、裁量が大きいため、時間の管理がしやすい傾向にあります。
さらに、公的機関である市役所や役所では、法律によって労働時間が厳しく管理されており、基本的に長時間労働が発生しにくい職場です。
働く環境が整備されている環境は安定した労働時間で働けるため、ワークライフバランスを重視したい人におすすめです。
残業が多い業界で働く懸念

ここでは、残業が多い業界で働くことに関する以下の懸念について解説します。
こうしたリスクを理解することで自身の働き方を見直し、より良い職場環境を選択するための判断材料にできるでしょう。
なお、すでに就職が決まっていても、残業時間の懸念がある業界・仕事だった場合はキャリチャンの就活支援サービス「再就活サポート」を活用してみてください。残業時間などの不安を解消できる求人を紹介し、前向きな気持ちで就職するための再就活をサポートします。
健康への悪影響
残業が多い業界で働く懸念として、健康面への深刻な影響が挙げられます。
慢性的な疲労や睡眠不足が続くと、体力が低下し、免疫力も落ちてしまいがちです。結果として風邪を引きやすくなったり、集中力が低下したりと、仕事の効率に影響を与えるでしょう。
また、ストレスが蓄積することで懸念されるのが、メンタルヘルスの悪化です。とくに、プレッシャーの大きい仕事では、うつ病や適応障害を発症するリスクが高まる傾向にあります。
さらに、運動不足や不規則な食生活が続くことで、生活習慣病のリスクも上昇するでしょう。高血圧や糖尿病などの健康問題が発生すると、長期的な働き方にも支障をきたす可能性があります。
健康を維持するためには、適度な休息と生活リズムの確保が重要です。過度な残業が続く環境では自身の健康管理が難しくなるため、働く環境を慎重に選びましょう。
プライベート時間の不足
残業が多い業界で働く懸念として、プライベートの時間が不足しがちということがあります。
長時間労働が続くと、仕事以外の時間を確保することが難しくなります。とくに、家族や友人と過ごす時間が減ることで、人間関係に影響が出てしまうでしょう。休日が不規則な業界では友人との予定が合わず、プライベートが充実しないと感じることも少なくありません。
さらに、趣味や自己投資のための時間を確保しにくくなる点も問題です。スキルアップのための勉強やリフレッシュするための時間が削られることで、仕事のモチベーション低下にもつながる可能性があります。
また、有給休暇が取りづらい職場ではまとまった休みが確保できず、旅行やリフレッシュの機会が制限されがちです。
このように長時間労働が常態化している職場では、プライベートの時間が不足しやすいと言えるでしょう。
キャリア形成への影響
長期的に見てキャリア形成に悪影響を及ぼす可能性があることも、残業が多い業界で働く上での懸念点です。残業が多い業界で働いていると、キャリアアップのための時間を確保することも難しくなります。
たとえば資格取得や自己研鑽のための学習時間が取れず、スキルアップの機会を逃してしまうこともあるでしょう。結果として、同じ職場に留まるしか選択肢がなくなり、キャリアの可能性が狭まるのです。
また、転職活動がしづらくなる点も大きな懸念として挙げられます。履歴書の作成や面接準備に時間を割く余裕がないため、良い求人を見つけても動けない状況に陥りがちです。
とくに、長時間労働が当たり前の業界では、転職のタイミングを逃しやすくなる傾向にあります。
さらに、業界特有のスキルに偏りがちになるリスクも見過ごせません。特定の分野に特化した仕事を続けることで他の業界への転職が難しくなり、選択肢が狭まる可能性があります。
将来的なキャリアの幅を広げたい場合は、残業が多い業界は避けた方がいいと言えるでしょう。
金銭面でのデメリット
残業が多い業界で働く懸念として、金銭面でマイナスになることが挙げられます。
長時間労働が、必ずしも金銭面でプラスになるとは限りません。むしろ、長時間働いても思うように収入が増えない場合もあります。長時間労働をしても金銭面が充実しないのは、いくつかの理由によるものです。
第一に、残業しているにもかかわらず収入が増えないケースがあります。たとえば、サービス残業の発生が理由です。企業によっては残業代が適切に支払われないことがあり、実際には長時間働いてもその分の賃金が得られないことがあります。
また、固定残業代が設定されている場合、既定の残業時間を超えない限り、残業しても定時で退社しても給料はまったく変わりません。そのため、残業しているにもかかわらず、時給換算で見ると逆に収入が減っている場合があります。
次に、残業が増えることで支出が増えてしまうこともあるでしょう。たとえば、長時間働くことが原因で家で食事をする時間がなくなり、外食が増えることがあります。その結果、食費がかさむことが考えられます。
残業をする=収入が増えると思われがちですが、実際はそうならないこともあるので、ちゃんと残業に見合った収入増加が起こっているか定期的な確認が必要です。
なお、固定残業代制度を採用している企業では、一定時間以上の残業をしても追加の報酬が発生しないケースがあるため注意しなければなりません。固定残業代について詳しく知りたい人は、以下のコラムもあわせてチェックしてみましょう。
残業が多い業界で働くことには「良さ」もある

長時間労働が多い業界はネガティブな印象を持たれがちですが、いくつかのメリットも存在します。ここでは、長時間労働がもたらすポジティブな側面は、以下の4点です。
残業による「良さ」を把握することで、就活の方向性や自身なりの選択肢も増えていくでしょう。
高収入を得やすい
残業が多い業界には、収入が増えやすいというメリットがあります。
残業代が適切に支払われる企業では、基本給に加えて時間外手当が加算されるため、同年代の平均よりも高い給与を得られる可能性が高いでしょう。
また、コンサルティング・IT・金融など、労働時間が長い業界はもともと給与水準が高く、努力次第で高収入を実現しやすい環境です。さらに、長時間労働をこなせる人材は評価されやすく、昇進・昇給のスピードが早まるケースも少なくありません。
収入を重視する人にとっては、ハードワークが直接的な経済的メリットにつながる点が魅力となるでしょう。ただし、あくまでも労働環境や給与体系が整っている企業を選ぶことが前提となっています。収入を重視する人にとっては、ハードワークが直接的な経済的メリットにつながる点が魅力となるでしょう。ただし、あくまでも労働環境や給与体系が整っている企業を選ぶことが前提となっています。
成長スピードが速くなる
残業をするメリットとして、長時間労働を経験すると実務経験を短期間で多く積めるため、スキルの習得が加速することが挙げられます。
一般的な労働時間では数年かかる経験を短期間で身につけることが可能になり、業界内での競争力を高められるでしょう。
また、タイトなスケジュールの中で業務をこなすことで、効率的な仕事の進め方や問題解決能力が養われます。短時間で成果を出すスキルが身につけば、将来的に労働時間を短縮しながら高い生産性を維持できるようになるでしょう。
さらに、プレッシャーがかかる環境で働くことで、精神的な耐性も強化されます。厳しい状況を乗り越えた経験はどの職場においても自信につながり、キャリアの成長を後押しする要素となるでしょう。
責任ある仕事を任されやすい
残業が多い業界で働くメリットとして、若いうちから重要な案件を担当する機会が増えることもあります。
長時間労働を経験することで業務の幅が広がり、早い段階で責任のあるポジションを任されることが少なくありません。
また、多忙な環境では意思決定を求められる場面が多く、自分で判断する力が鍛えられます。業務のスピードが求められる分、リーダーシップや決断力が身につきやすいでしょう。加えて、実績を積み上げることで評価されやすく、管理職への昇進がスムーズに進む可能性が高まります。
責任のある仕事を通じてキャリアアップを目指す人にとっては、成長のチャンスが多い環境と言えるでしょう。労働時間の長さだけでなく、自身のスキル向上の機会として活用する意識が重要です。
チームワークが強くなる
残業が多い業界で働くメリットとして、長時間労働を共にすることで、職場の仲間との結束が強まることがあります。
とくに、プロジェクト単位で動く業界では、困難な状況を乗り越えた経験が信頼関係を深める要因となるでしょう。
また、タイトなスケジュールの中で業務を進めるには、協力体制が欠かせません。チームでの役割分担を効率的に行うスキルが自然と身につき、仕事の進め方が洗練されていきます。さらに、長時間労働の末に成功したプロジェクトでは、強い達成感を得られるでしょう。
仲間とのつながりを大切にしながら仕事に取り組むことで、単なる労働時間の長さを超えた充実感を感じられます。
残業が多い業界の傾向を把握したうえで就活を
業界によって、残業の発生しやすさには明確な違いがあります。納期やクライアント対応の影響を受けやすい業界は長時間労働が常態化しやすく、一方で労働時間が管理されている業界ではワークライフバランスを確保しやすいのが特徴です。
残業が多い業界には、健康リスクやプライベート時間の確保が難しいといったデメリットがある一方で、収入が増えたり、スキルを短期間で習得できたりといったメリットも存在します。
自分にとって何を優先するのかを明確にし、業界ごとの働き方を理解したうえで就活を進めることが大切です。
なお、長時間労働を避けたい場合は、企業の残業実態や制度の整備状況を事前に確認すると良いでしょう。
「就活相談サポート」に参加しよう!
この記事の監修者

廣瀬 舞
株式会社ジールコミュニケーションズ
HR事業部マネージャー
大学卒業後、教育機関を経て入社。7年間、キャリアカウンセラーとして新卒・中途・既卒求職者の就職を支援し、これまでに4000名以上の求職者を担当し内定まで導いている。女性ならではの親切丁寧な対応が定評を呼んでおり信頼度が厚い。
就活支援の得意分野は「面接対策」。特に現代ならではの動画面接、オンライン面接の対策実績は1000社以上、2000名以上を支援してきた実績がある。
また、これらの知見を活かして学校におけるキャリアガイダンス セミナー内容の監修、講師を務めるなど、幅広くキャリア育成に尽力している